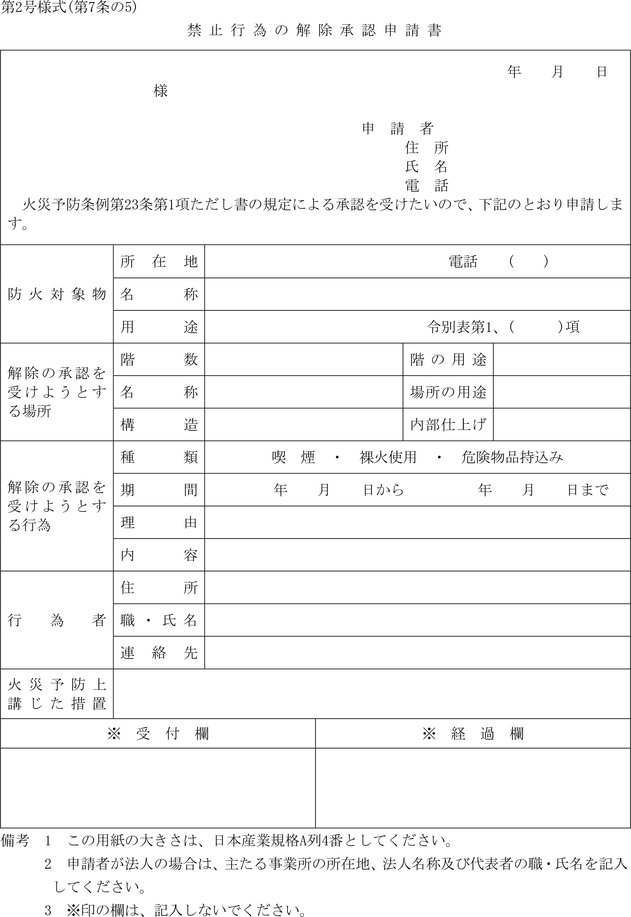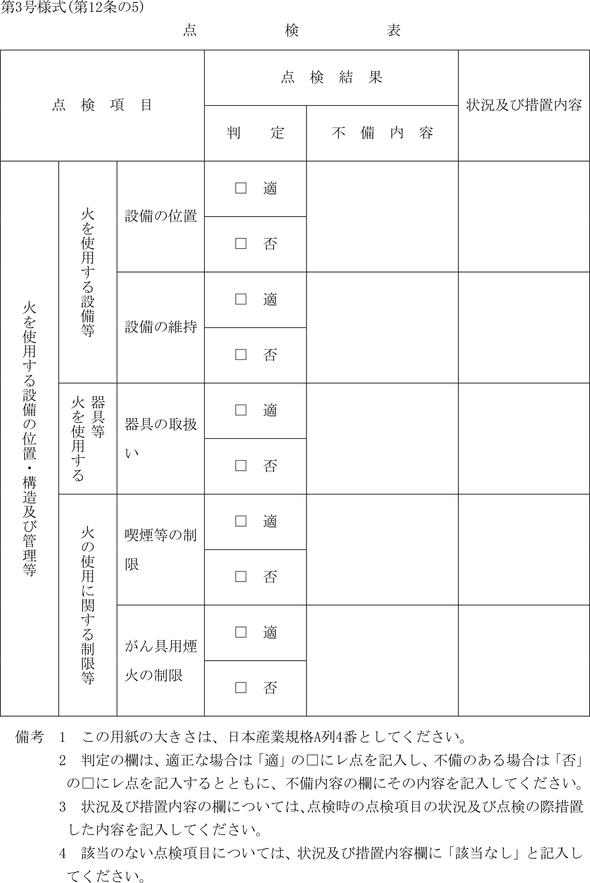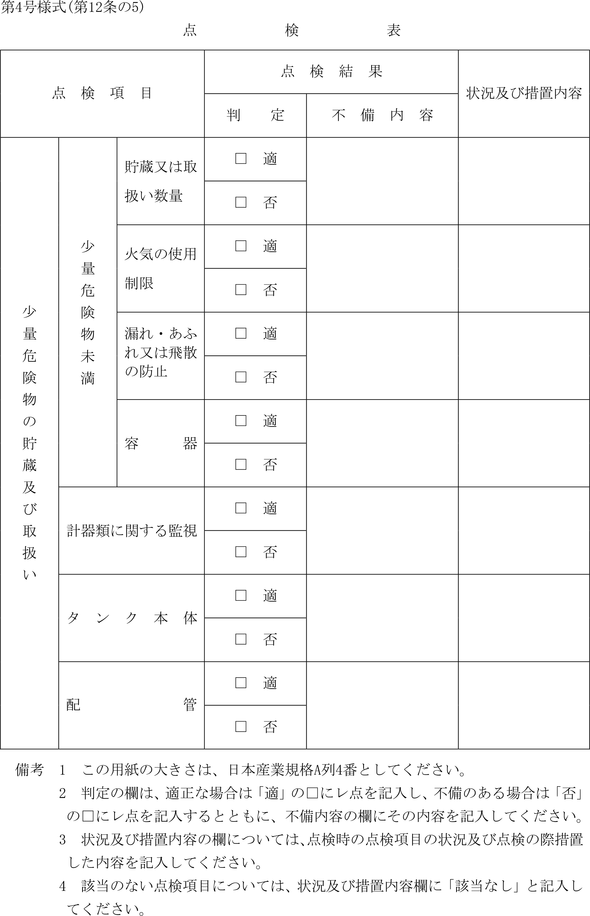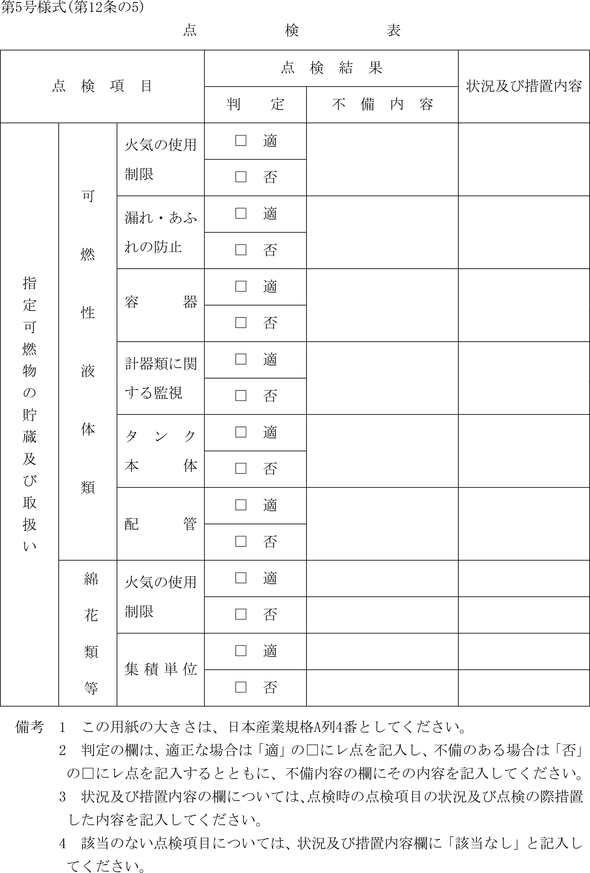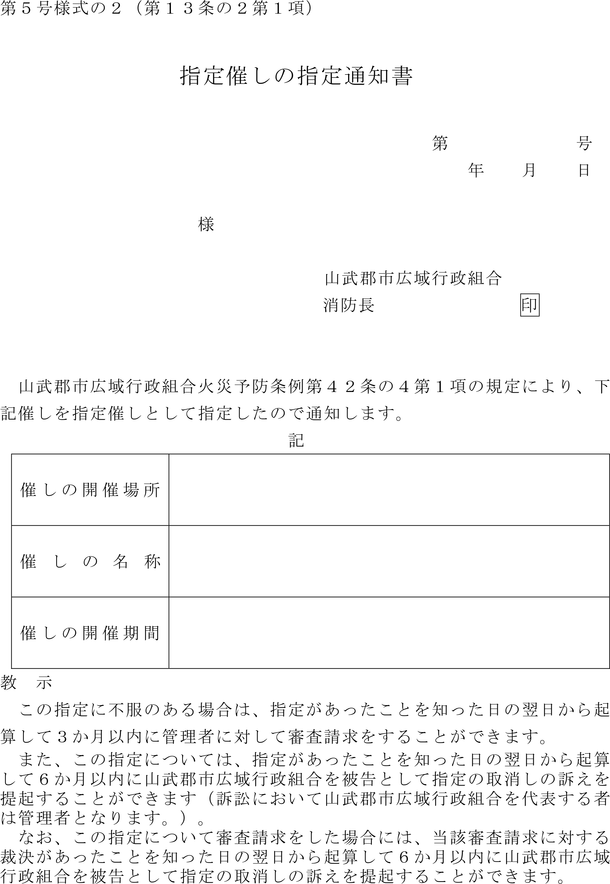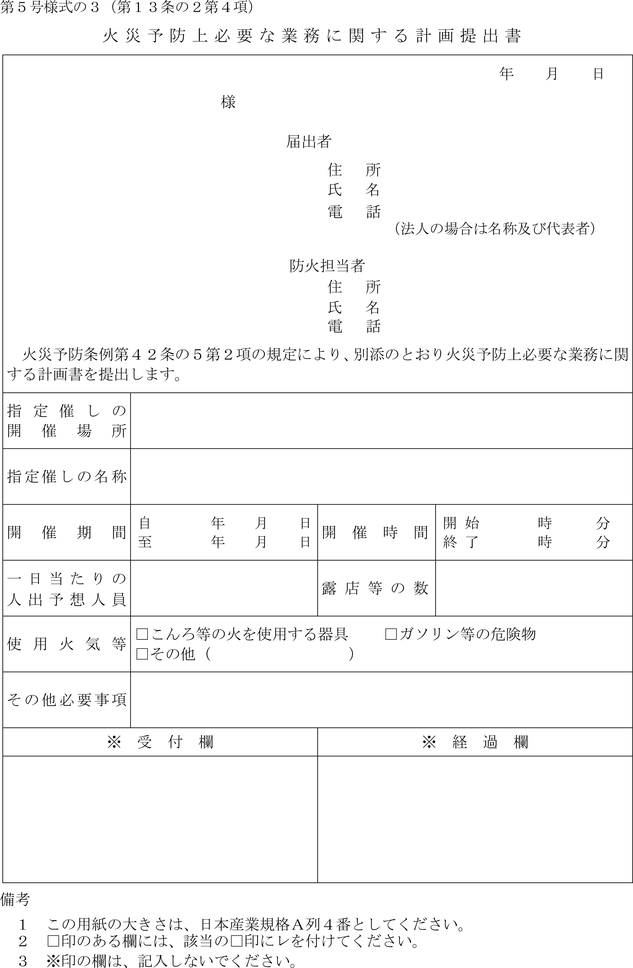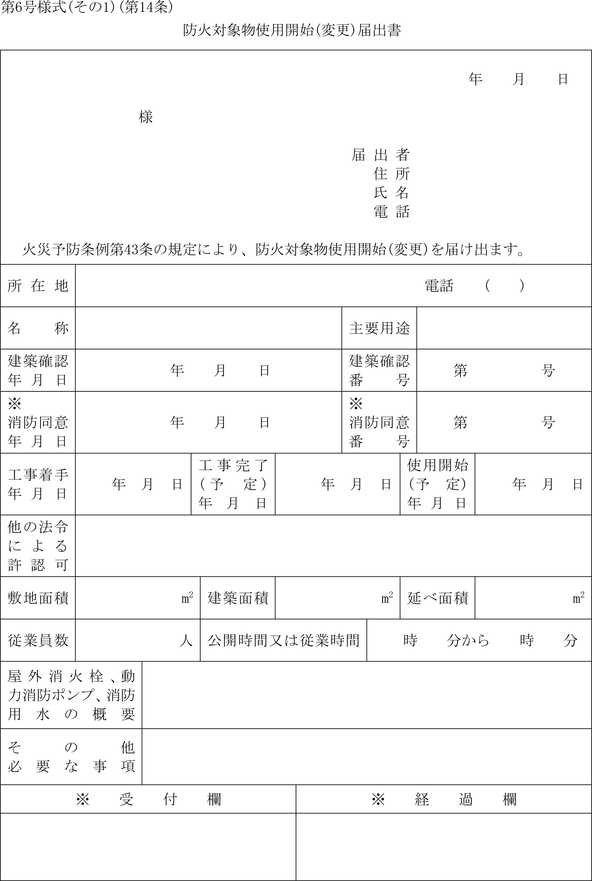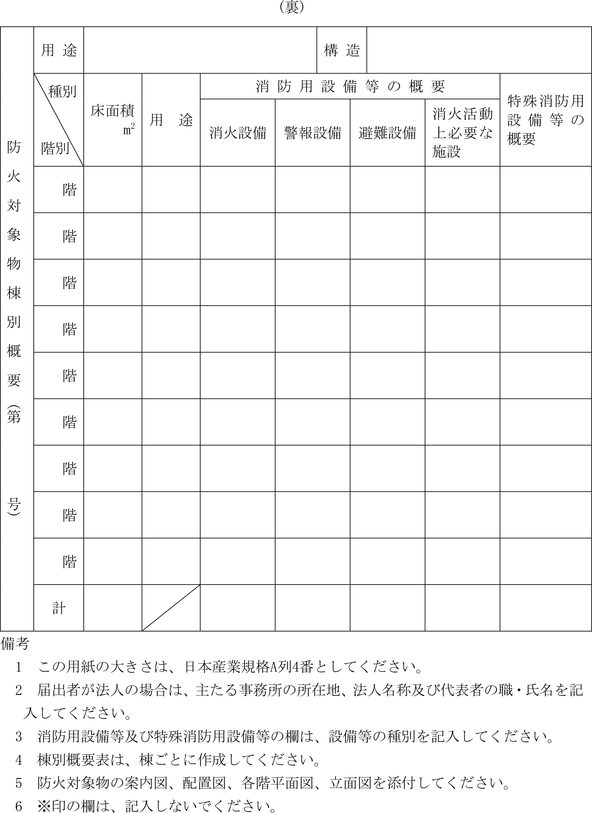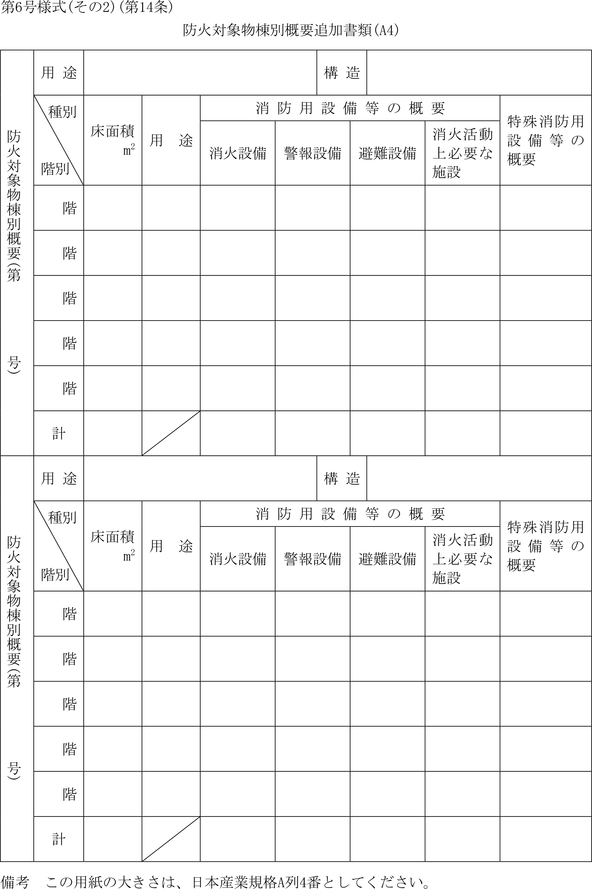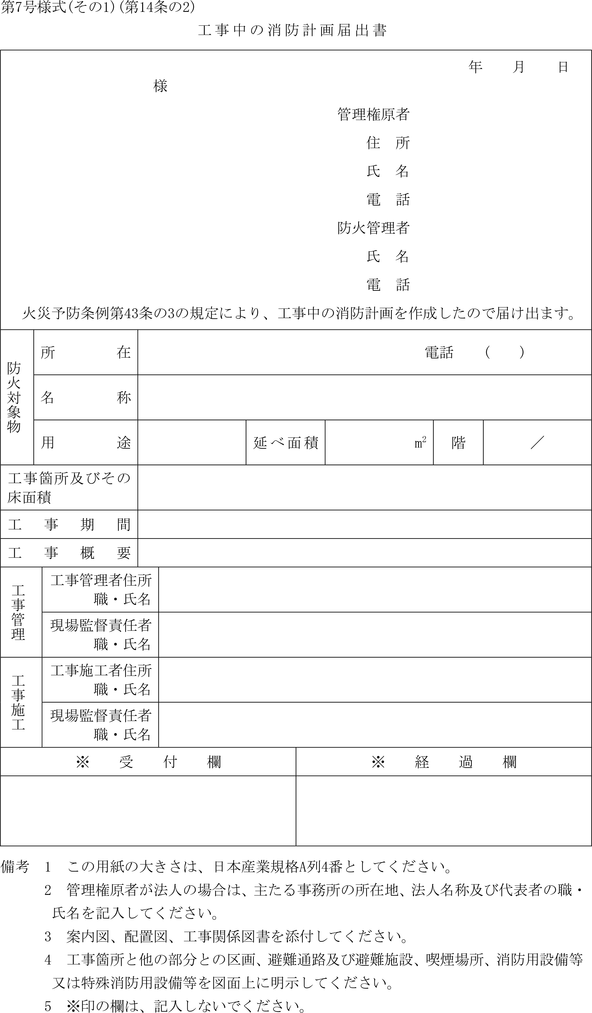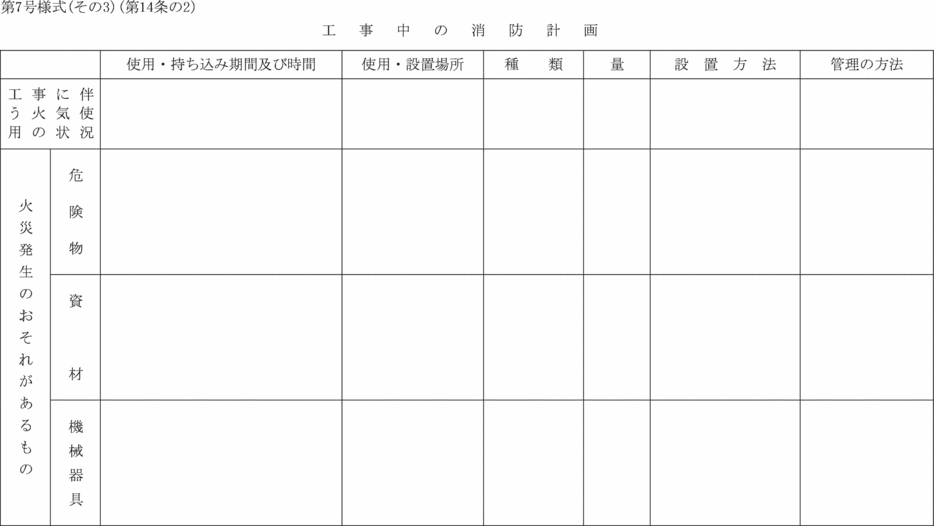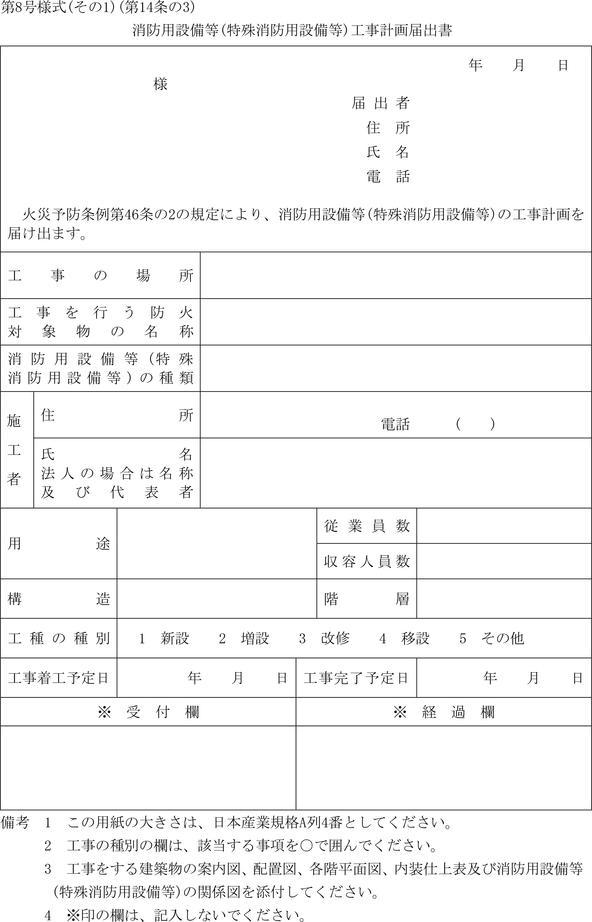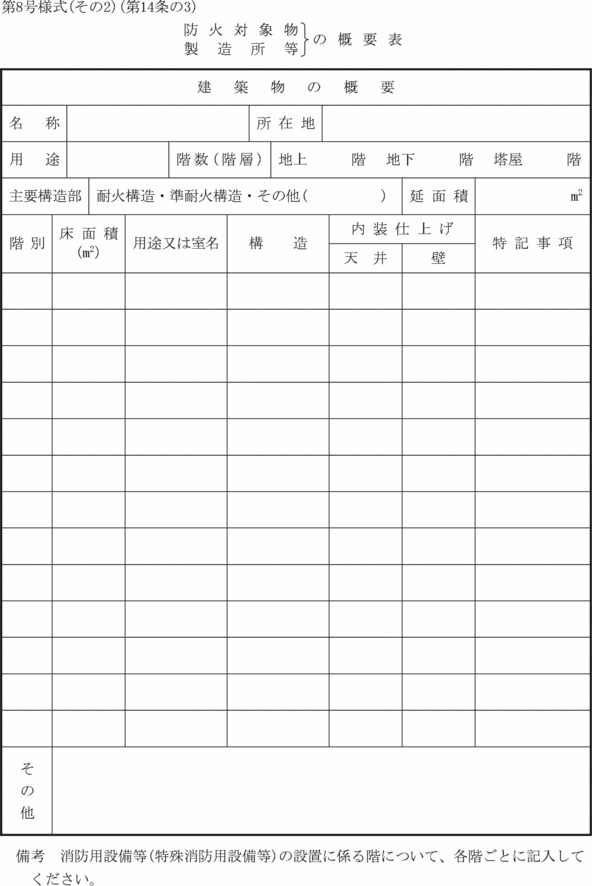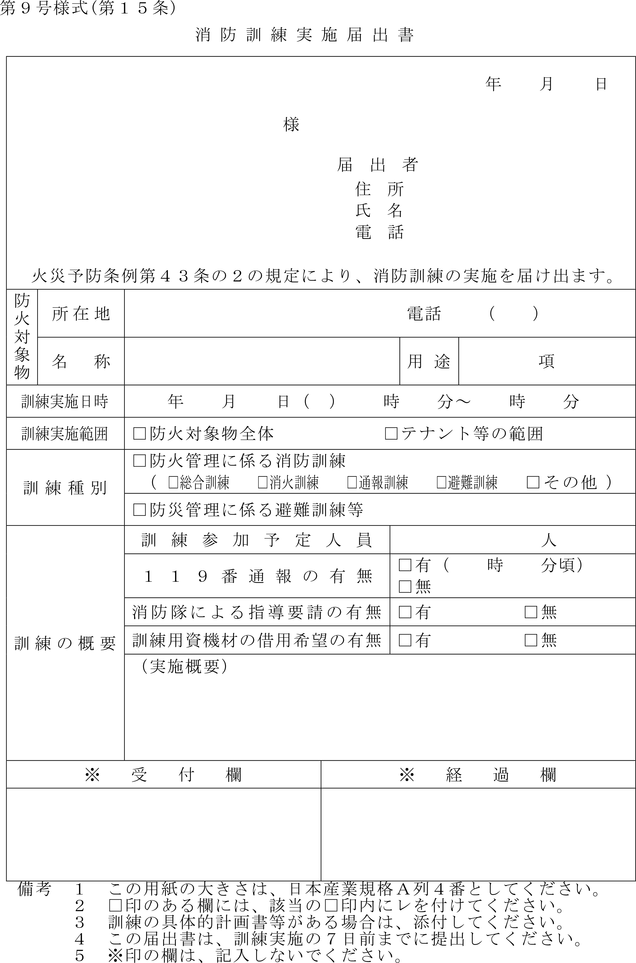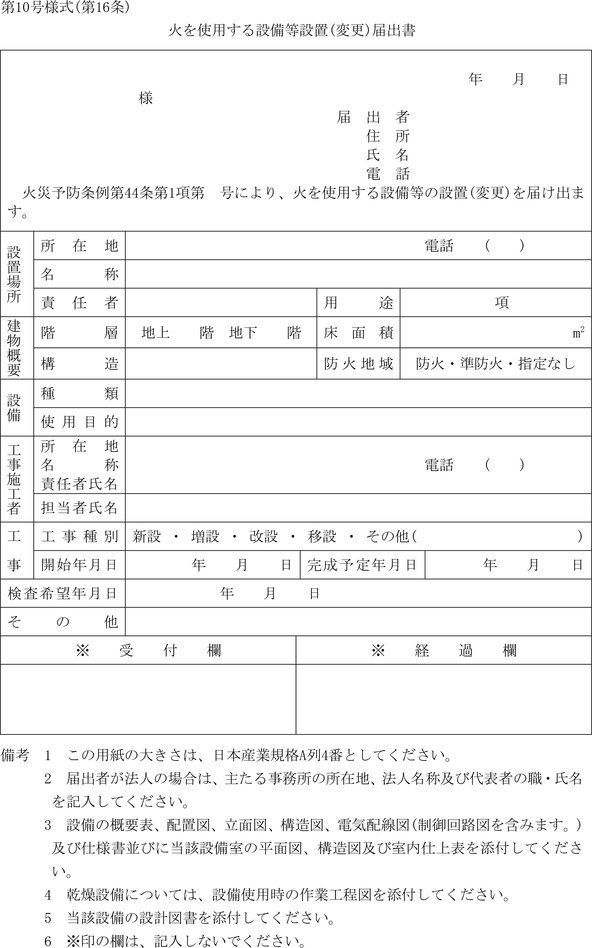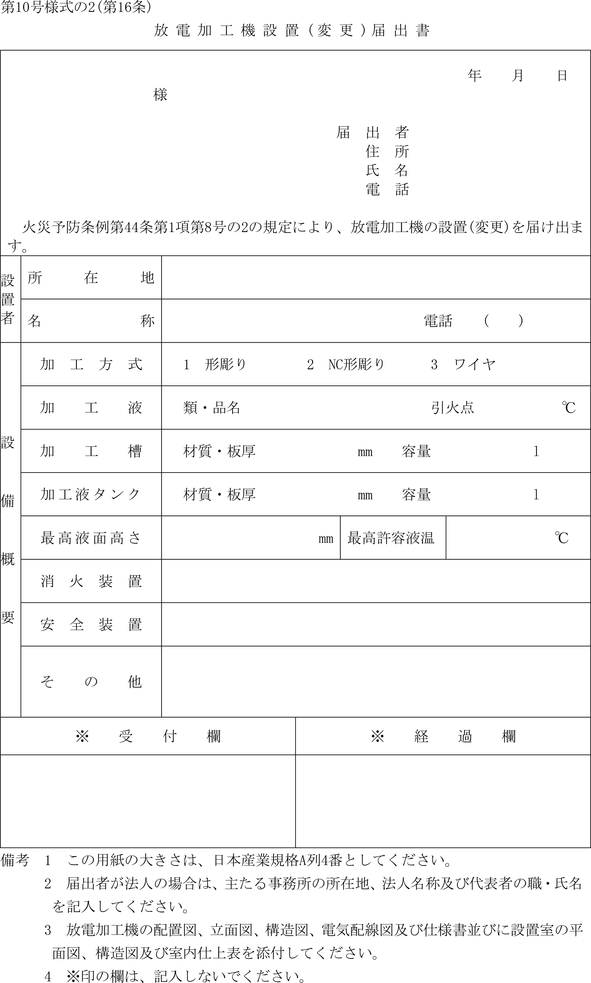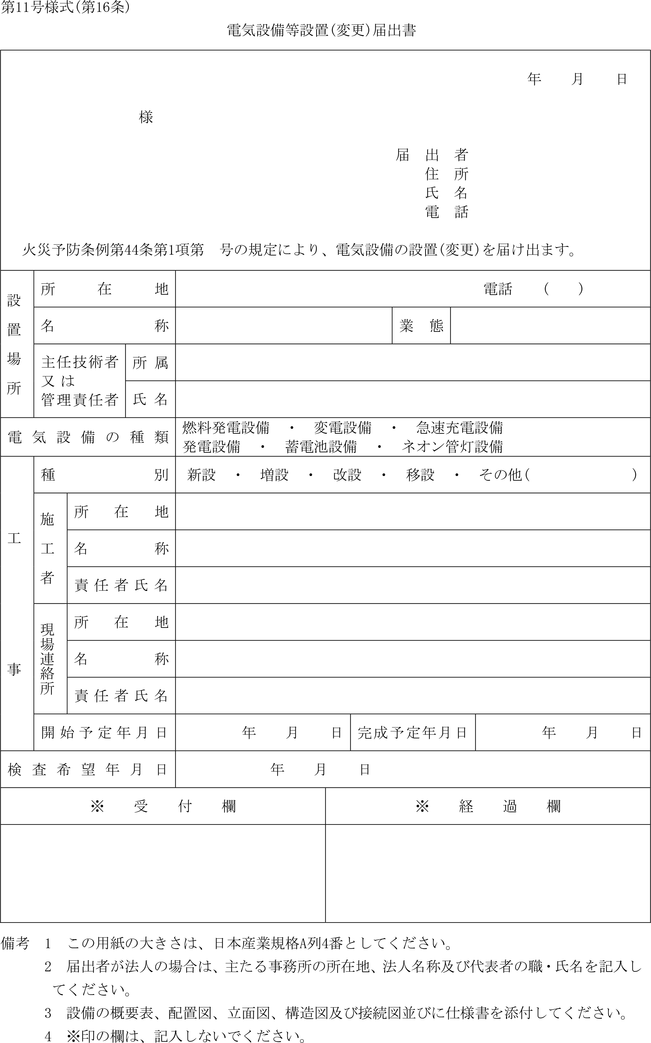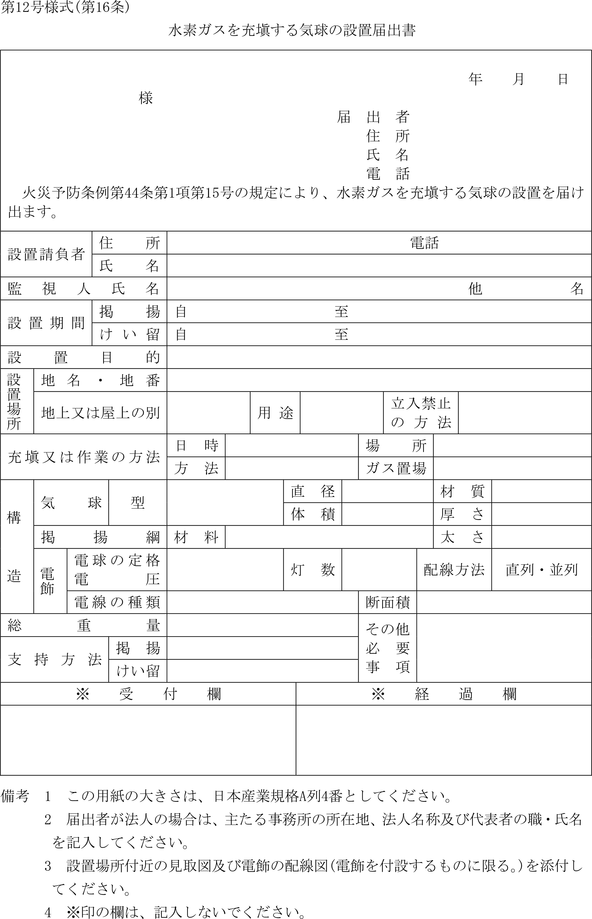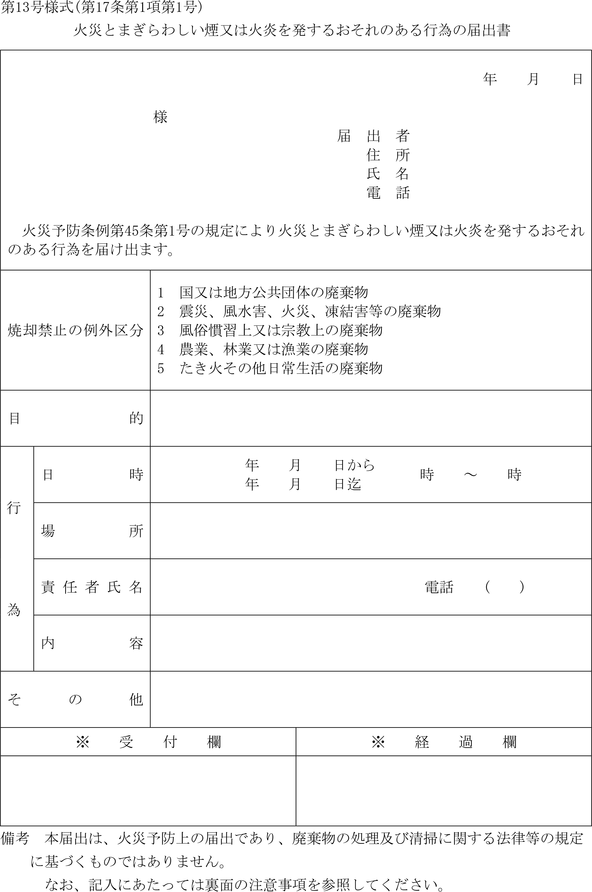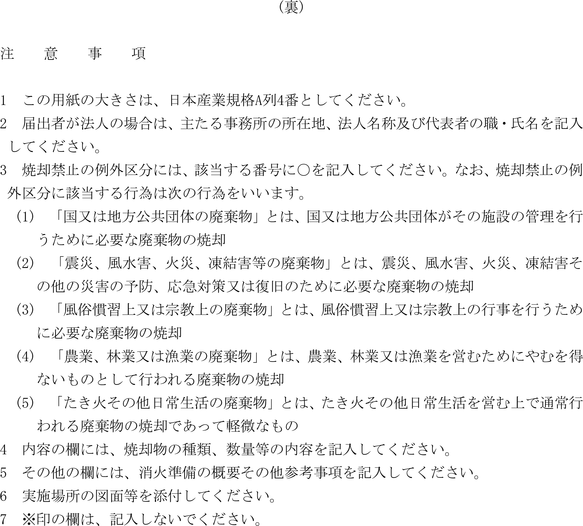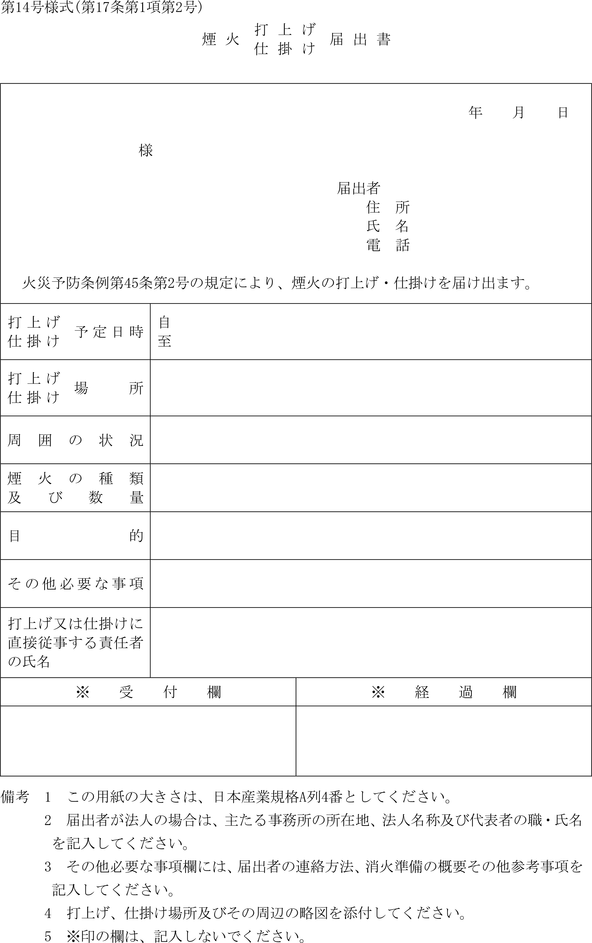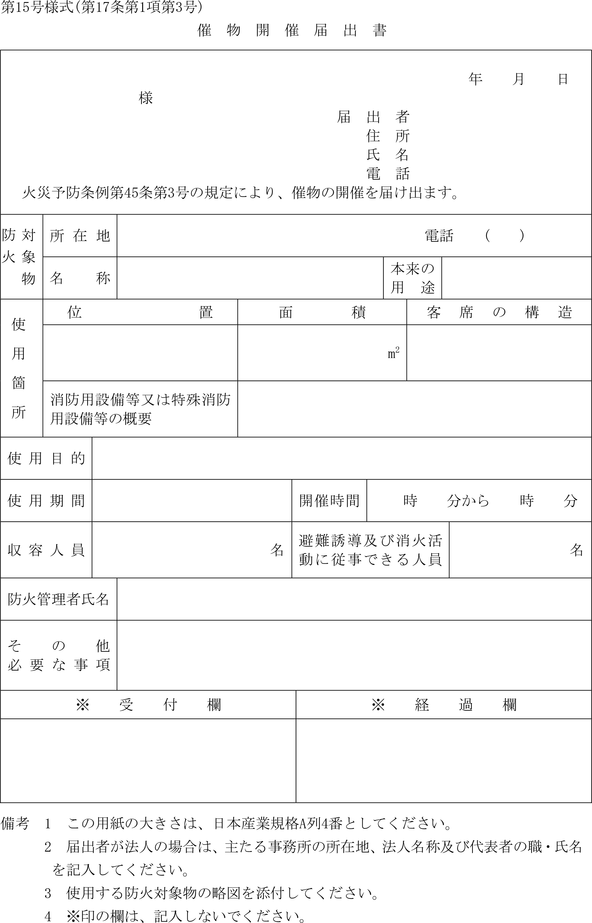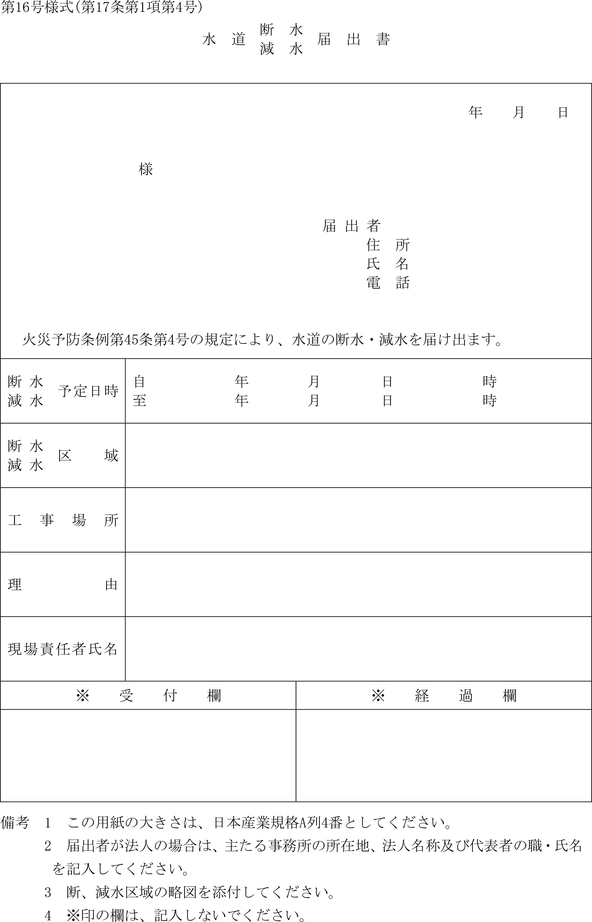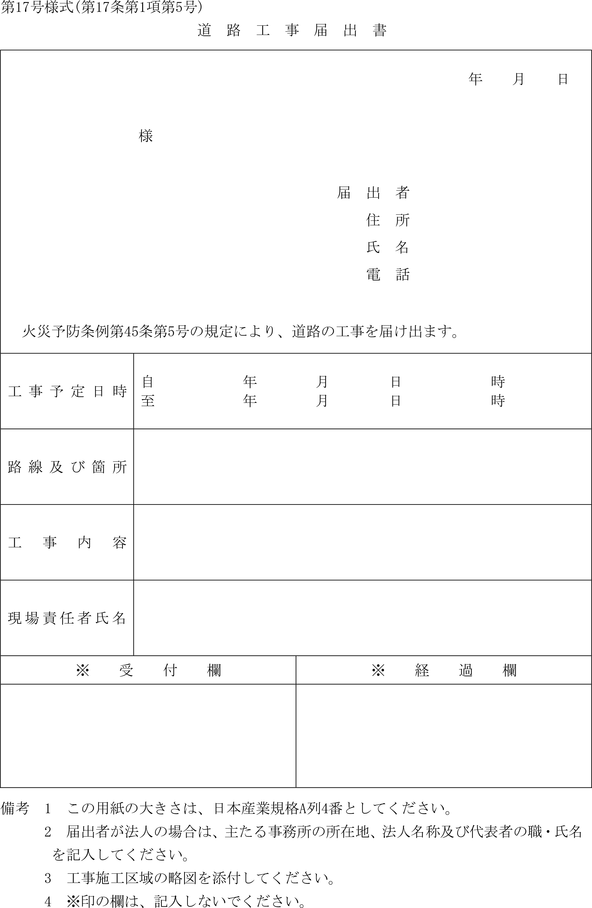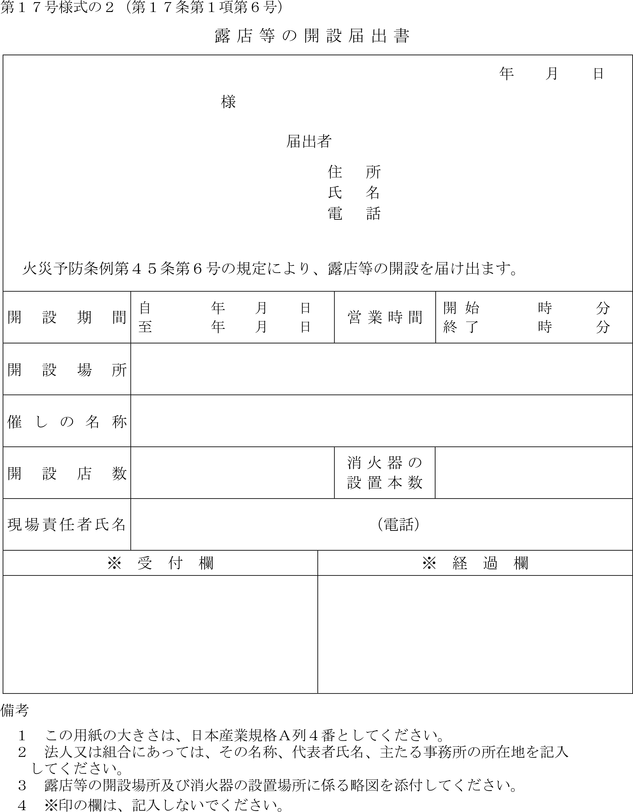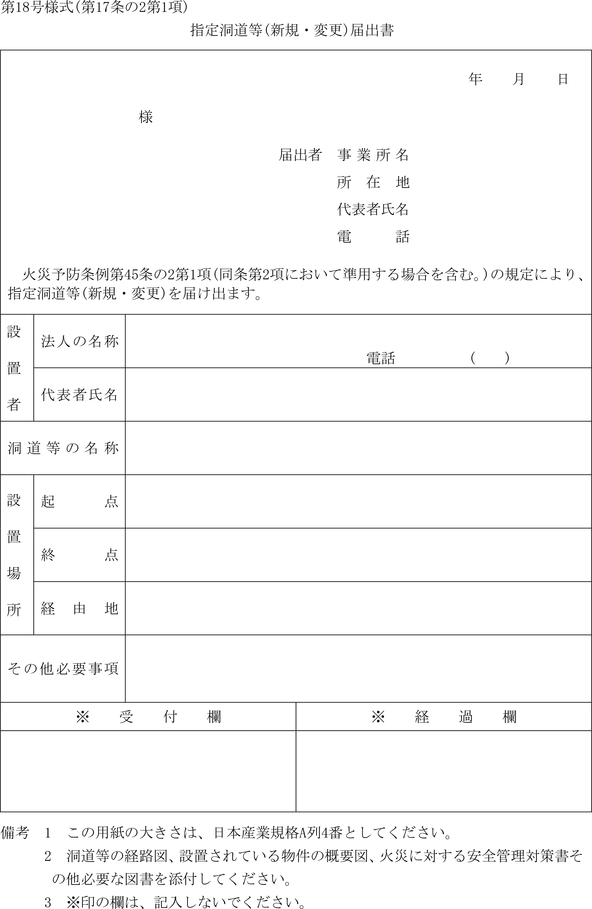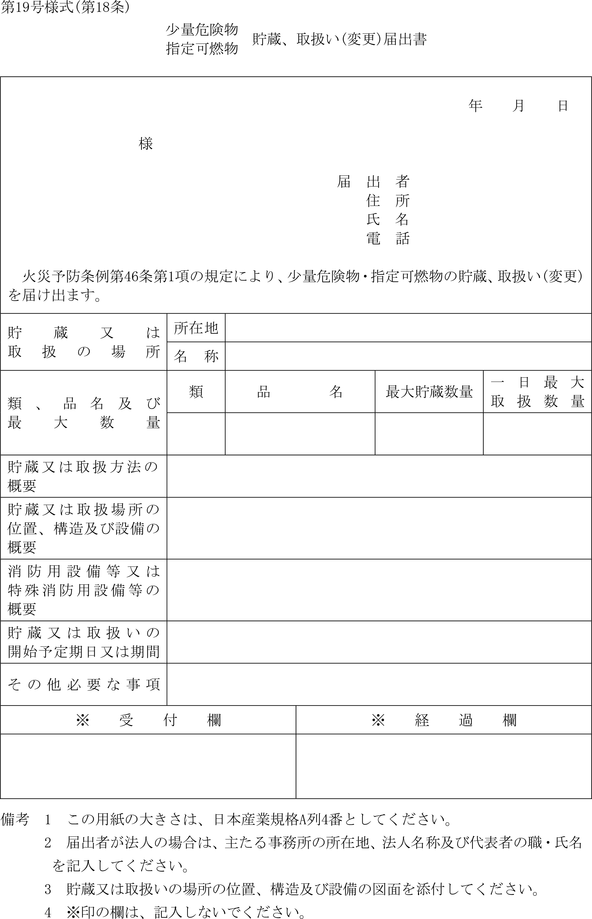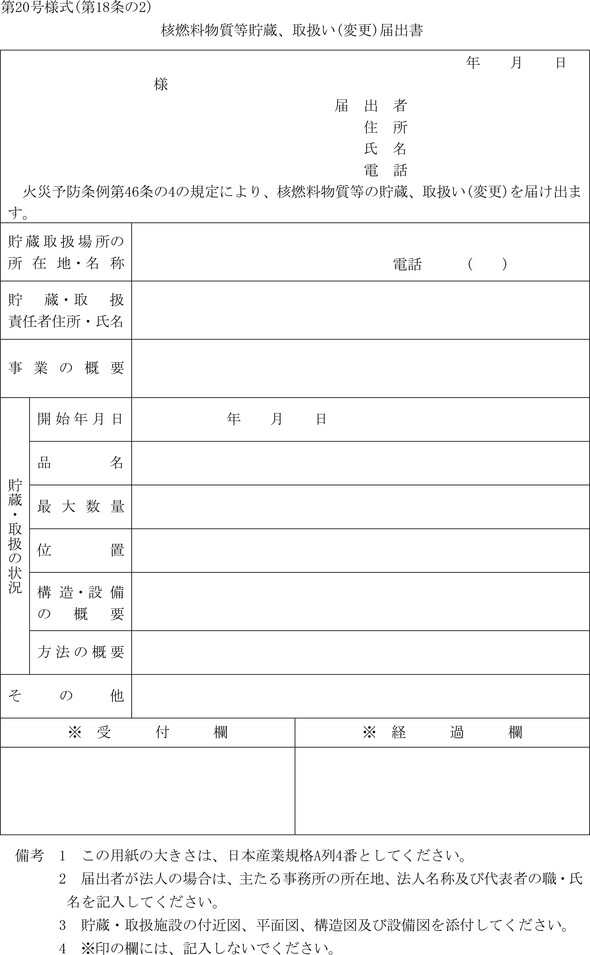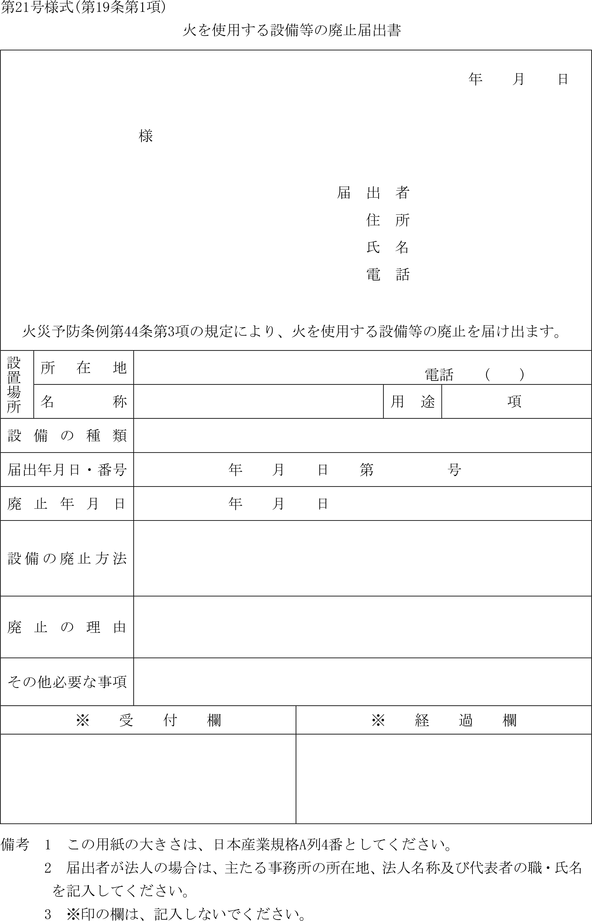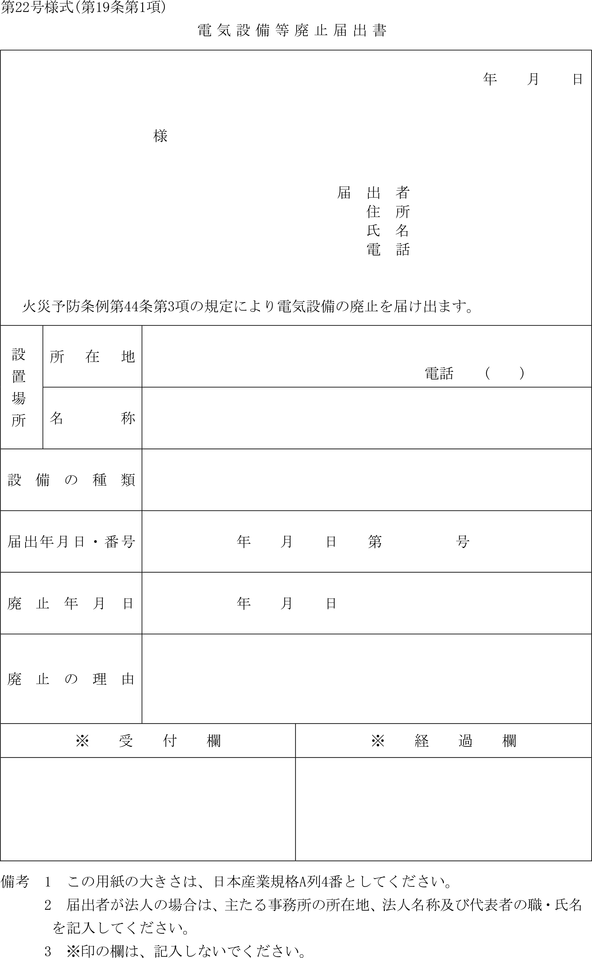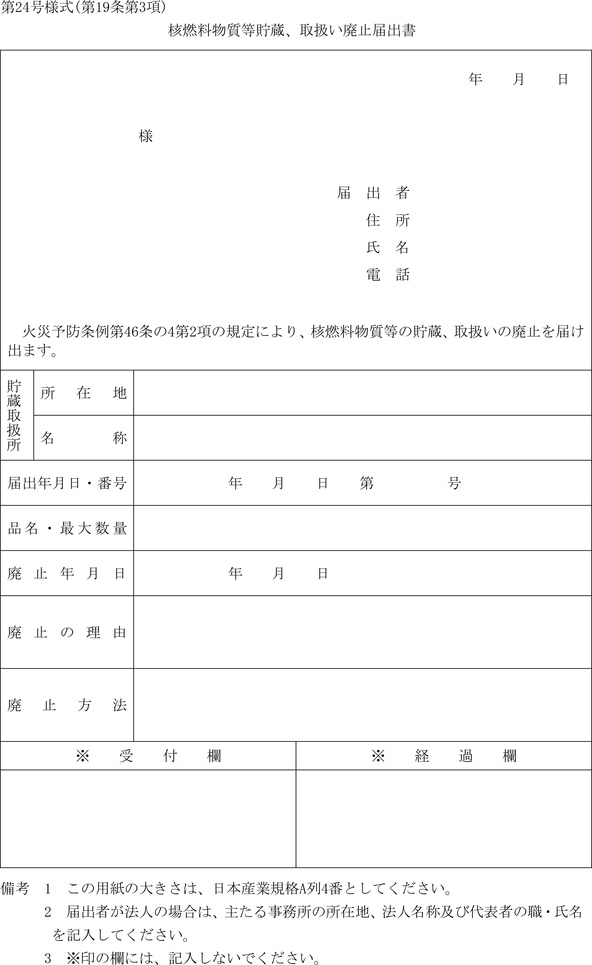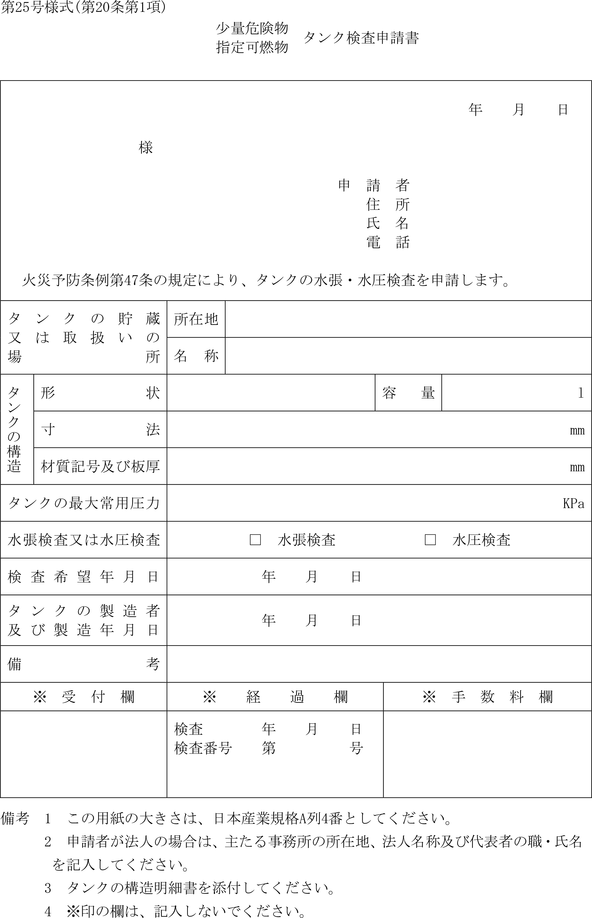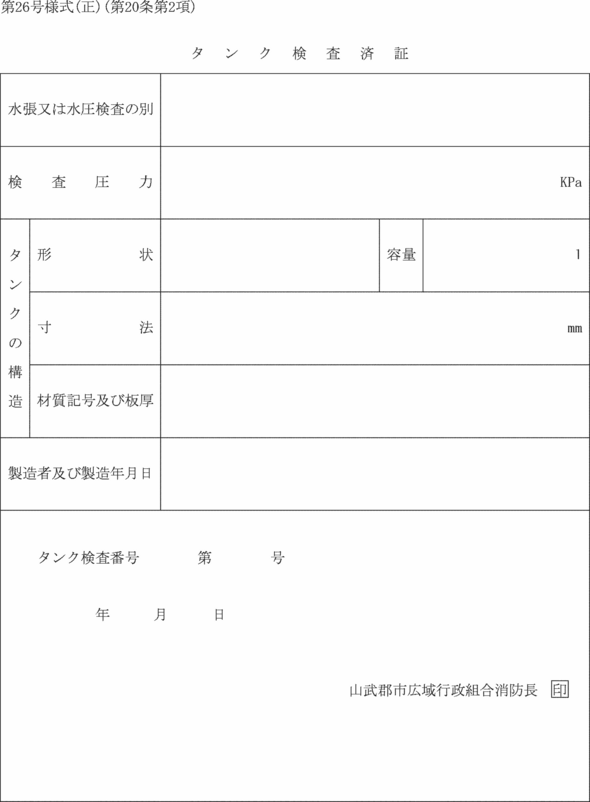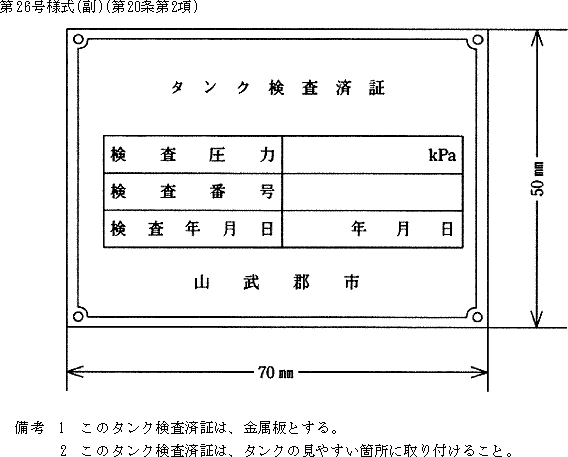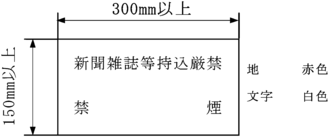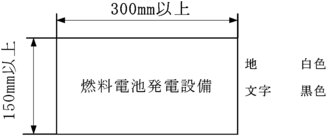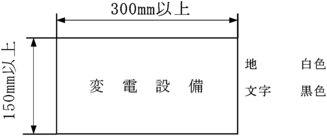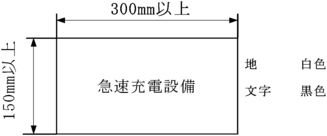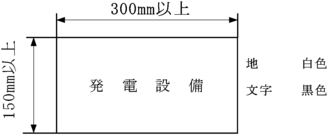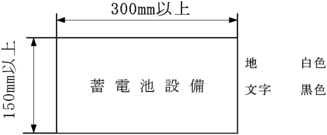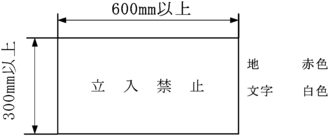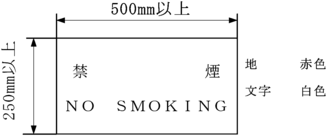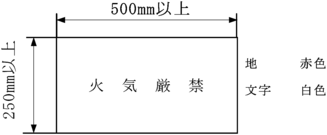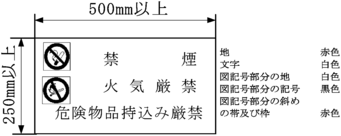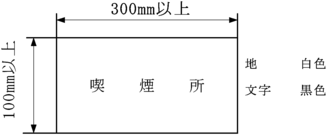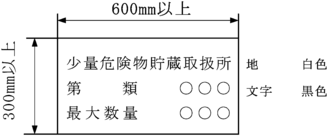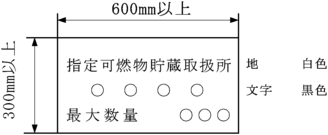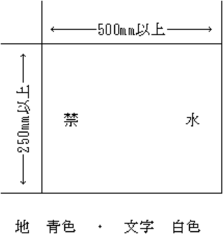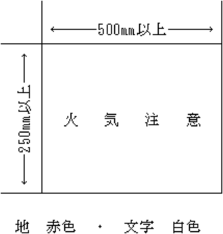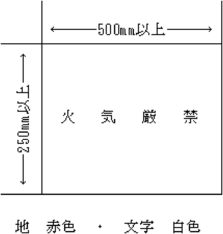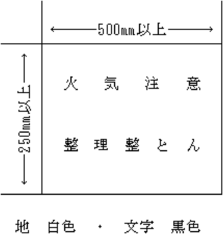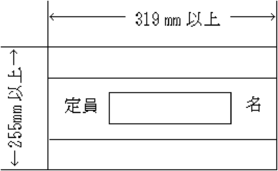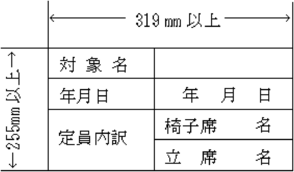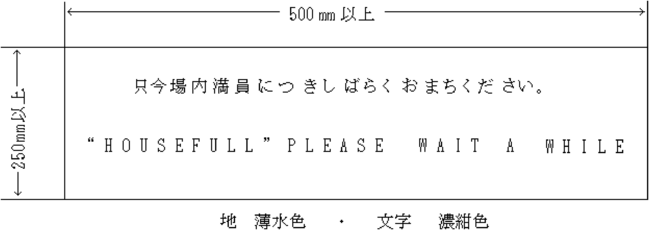○山武郡市広域行政組合火災予防条例施行規則
平成2年5月7日規則第5号
注 平成19年9月から改正経過を注記した。
山武郡市広域行政組合火災予防条例施行規則
(目的)
第2条 削除
削除〔平成22年規則9号〕
(申請書等の提出)
第3条 条例及びこの規則に基づいて消防長又は消防署長に提出する申請書又は届出書は、別に定めがある場合を除き2通を作成し提出するものとする。
一部改正〔平成22年規則9号〕
(不燃区画室内に設ける火を使用する設備)
(1) 火を使用する設備の周囲にあっては5メートル以上、上方にあっては10メートル以上の空間を保有すること。
(2) 屋外又は主要構造部を不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)とした建築物の屋上に設置する火を使用する設備の周囲にあっては3メートル、上方にあっては5メートル以上の空間(開口部のない不燃材料の外壁等に面する場合を除く。)を保有すること。
(3) 火を使用する設備を設置する部分に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること。
一部改正〔平成24年規則1号・30年8号〕
(標識等)
2
条例第31条の2第2項第1号(
条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び
第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、危険物(消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。以下同じ。)にあっては類、品名及び最大数量を、指定可燃物(
条例別表第8の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)にあっては品名及び最大数量をそれぞれ記載するとともに、危険物又は指定可燃物の性状に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、これらの様式は、
別表第2に定めるとおりとする。
危険物又は指定可燃物の種類 | 防火上の記載事項 |
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第1条の5第5項の水との反応試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。) | 禁水 |
第2類の危険物(引火性固体を除く。) | 火気注意 |
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。以下同じ。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類等(条例第33条第2項第1号に規定する可燃性固体類等をいう。) | 火気厳禁 |
指定可燃物(可燃性固体類等を除く。) | 火気注意整理整とん |
一部改正〔平成22年規則9号・24年9号〕
第5条 削除
(天蓋及び排気ダクトの構造)
(1) 天蓋及び排気ダクトの構造
ア ステンレス又はこれと同等以上の耐食性を有する不燃材料で造られていること。
イ 建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品から10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、次の(ア)又は(イ)に適合する場合はこの限りでない。
(ア) 天蓋とこれに面する可燃性の部分の間に厚さ6ミリメートル以上の石綿板又はこれと同等以上の断熱性の不燃材料を用いた場合
(イ) 排気ダクトをロックウール又はこれと同等以上の断熱材料で厚さ50ミリメートル以上被覆した場合
(2) 火炎伝送防止装置は、防火ダンパー又は自動消火装置(強化液、泡、ハロゲン化物、粉末、二酸化炭素)のいずれかとする。
(3) 防火ダンパーは、天蓋から2メートル以内の点検が容易にできる位置とし、作動時は、排気ファンが停止する構造とすること。
(4) 第2号の自動消火装置は、日本消防設備安全センターの認定合格品を用いること。
(タンクの内容積の計算方法)
一部改正〔平成22年規則9号・24年1号〕
(地震動等により作動する安全装置を設ける火を使用する設備)
(地震動等により作動する安全装置の基準)
(1) 地震動等により作動する安全装置は、感震装置及び消火装置又は燃料供給停止装置により構成されていること。
(2) 前号の感震装置は、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。)S3021に定める振動を有するものであること。ただし、
条例第3条の2第2項のふろがまに設けるときは日本産業規格S3018に、
条例第5条第2項のストーブに設けるときは日本産業規格S2039に定める振動の性能を有すること。
(3) 第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動して、速やかに、消火し、かつ、燃料の供給が停止するものであること。
(4) 第1号の燃料供給停止装置は、第2号の感震装置と連動して、速やかに、燃料の供給を遮断し、燃焼が停止するものであること。
(5) 第1号の感震装置、消火装置及び燃料供給停止装置は、経過年数による変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。
一部改正〔平成24年規則1号・令和元年3号〕
(変電設備の保有距離)
種別 | 前面 | 背面 | 相互間 | 2列以上設ける場合の列の相互間 |
配電盤 | 高圧 | 1.2メートル以上 | 0.8メートル以上 | ―――― | 1.8メートル以上 |
低圧 | 1.0メートル以上 | 0.8メートル以上 | ―――― | 1.8メートル以上 |
変圧器 | 0.6メートル以上 | ―――― | 0.1メートル以上 | 1.0メートル以上 |
保有距離を確保すべき部分 | 保有距離 |
前面又は操作面 | 1.0メートル以上 |
点検面 | 0.6メートル以上 |
換気口(注) | 0.2メートル以上 |
注 前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。
追加〔平成24年規則1号〕
(簡易湯沸設備と給湯湯沸設備の区分)
第7条の4 条例第8条及び
第8条の2に規定する簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備は、次の区分によるものとする。
(1) 簡易湯沸設備は、入力12キロワット以下の湯沸設備をいう。
(2) 給湯湯沸設備は、前号以外の湯沸設備をいう。
(地震動等により作動する安全装置を設ける器具)
追加〔平成22年規則9号〕
(地震動等により作動する安全装置の基準)
第7条の4の3 条例第18条第2項の規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地震動等により作動する安全装置は、感震装置及び消火装置により構成されていること。
(2) 前号の感震装置は、前条に掲げる器具のうち、ストーブに設けるものにあっては、日本産業規格S2019に、こんろに設けるものにあっては、日本産業規格S2016に定める振動の性能を有するものであること。
(3) 第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動して、速やかに、消火するものであること。
(4) 第1号の感震装置及び消火装置は、経過年数による変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。
追加〔平成22年規則9号〕、一部改正〔令和元年規則3号〕
(危険物品等)
第7条の5 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に次の各号に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合に、
同条同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(
別記第2号様式)により申請しなければならない。
(1) 法別表第1品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの及び
条例別表第8に掲げる指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に定める可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具煙火
一部改正〔平成22年規則9号〕
(がん具用煙火の貯蔵容器)
第7条の6 条例第26条第3項の規定によりがん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合の容器の基準は、次のとおりとする。ただし、店頭において販売のため陳列するものについては、第2号は適用しない。
(1) 堅固に造り、その内面には鉄類を表さないこと。
(2) 遮光性を有するもので造るか、又は覆うこと。
(3) 外面に火気に対して注意を要する旨表示すること。
(定温式住宅用火災警報器の規格、設置及び維持に関する基準)
第7条の7 条例第29条の5第2項に規定する定温式住宅用火災警報器で規則で定めるもの(以下この条において「定温式住宅用火災警報器」という。)は、住宅における火災を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器であって、感知部、警報部等で構成されたもので、一局所の周囲の温度が一定の温度以上になったときに火災が発生した旨の警報を発するものとし、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号)第3条(第13号から第15号までを除く。)及び第4条の規定のほか、次項から第4項までに定める基準に適合するものでなければならない。
2 定温式住宅用火災警報器は、次に掲げる試験に合格するものでなければならない。
(1) 0度以上40度以下の周囲の温度において機能に異常を生じないこと。
(2) 耐食性能を有する定温式住宅用火災警報器にあっては、5リットルの試験器の中に濃度40グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を500ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸1対蒸留水35の割合に溶かした溶液156ミリリットルを1,000ミリリットルの水に溶かした溶液を1日2回10ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において4日間放置する試験を行った場合、機能に異常を生じないこと。この場合において、当該試験は、温度45度の状態で行うこと。
(3) 次に掲げる試験に合格すること。
ア 通電状態において、全振幅1ミリメートルで毎分1,000回の振動を任意の方向に10分間連続して加えた場合、適正な監視状態を継続すること。
イ 無通電状態において、全振幅4ミリメートルで毎分1,000回の振動を任意の方向に60分間連続して加えた場合、構造又は機能に異常を生じないこと。
(4) 任意の方向に最大加速度50重力加速度の衝撃を5回加えた場合、機能に異常を生じないこと。
(5) 外部配線端子を有する定温式住宅用火災警報器にあっては、通電状態において、次に掲げる試験を15秒間行った場合、機能に異常を生じないこと。
ア 内部抵抗50オームの電源から500ボルトの電圧をパルス幅1マイクロ秒、繰返し周期100ヘルツで加える試験
イ 内部抵抗50オームの電源から500ボルトの電圧をパルス幅0.1マイクロ秒、繰返し周期100ヘルツで加える試験
(6) 通電状態において、温度40度で相対湿度95パーセントの空気中に4日間放置した場合、適正な監視状態を継続すること。
(7) 定温式住宅用火災警報器の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗について、直流500ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が50メガオーム以上であること。
(8) 定温式住宅用火災警報器の充電部と金属製外箱との間の絶縁耐力が、50ヘルツ又は60ヘルツの正弦波に近い実効電圧500ボルト(定格電圧が60ボルトを超え150ボルト以下のものにあっては、1,000ボルト、定格電圧が150ボルトを超えるものにあっては、定格電圧に2を乗じて得た値に1,000ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、1分間これに耐えるものであること。
(9) 前2号に定める試験は、次に掲げる条件の下で行うこと。
ア 温度5度以上35度以下
イ 相対湿度45パーセント以上85パーセント以下
3 定温式住宅用火災警報器の感度は、次の試験に合格するものでなければならない。
(1) 81.25度の風速1メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、40秒以内(壁面に設置するものにあっては、次式で定める時間t秒以内)で火災警報を発すること。
t=4010g10(1+(65-θr)/16.25)/10g10(1+65/16.25)
注 θrは、室温(度)を表す。
(2) 50度の風速1メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、10分以内に作動しないこと。
4 定温式住宅用火災警報器には、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示すること。この場合において、第5号及び第6号に掲げる事項は、定温式住宅用火災警報器を設置した状態において当該事項を容易に識別できる大きさで表示されていなければならない。
(1) 定温式住宅用火災警報器という文字
(2) 製造年
(3) 製造事業者の氏名又は名称
(4) 耐食性能を有するものにあっては、耐食型という文字
(5) 交換期限(自動試験機能を有するものを除く。)
(6) 自動試験機能を有するものにあっては、自動試験機能付という文字
(7) 前項の規定に適合することを第三者が確認した場合にあっては、その旨及び当該第三者の名称
5 定温式住宅用火災警報器は、次に掲げる位置に設置しなければならない。
(1) 天井(天井がない場合にあっては、屋根。以下この号において同じ。)又は壁の屋内に面する部分の次のいずれかの位置
ア 壁又ははりから0.4メートル以上離れた天井の屋内に面する部分
イ 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分
(2) 前号に掲げる位置のほか、次に掲げる位置以外の位置
ア 著しく高温となる位置その他定温式住宅用火災警報器の機能に支障を及ぼすおそれのある位置
イ 点検その他維持管理に支障を及ぼす位置
6 前各項に規定するもののほか、定温式住宅用火災警報器は、
条例第29条の3第5項に規定する基準により設置し、及び維持しなければならない。
全部改正〔平成24年規則1号〕
(熱感知器の規格、設置及び維持に関する基準)
第7条の8 条例第29条の5第2項に規定する熱感知器で規則で定めるもの(次項及び第3項において「熱感知器」という。)は、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の基準を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この項において「感知器等規格省令」という。)第2条第5号に規定する定温式スポット型感知器であって、公称作動温度が60度又は65度のもので、かつ、感知器等規格省令第14条第2項に規定する特種の試験に合格したものとし、火災により生ずる熱を感知した場合に、住宅用防災報知設備の受信機(
条例第29条の4第4項第1号に規定する受信機をいう。)に火災信号を発信するものでなければならない。
2 熱感知器は、前条第5項各号に規定する位置に設置しなければならない。
追加〔平成24年規則1号〕
(タンクの結合部分に損傷を与えない設置方法)
(1) 配管とタンクの結合部分には、可撓性の継手(以下「可撓性継手」という。)が設けられていること。
(2) 配管が著しく細く可撓性継手を設けることができない場合は、当該配管に銅管等を用いタンク直近部分をループ状とする等十分な緩衝性を有する措置が設けられていること。
一部改正〔平成22年規則9号〕
(通気管等)
(1) 管の内径は、20ミリメートル以上とすること。
(2) 先端の位置は、地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓、その他の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。
(3) 先端の構造は、雨水の浸入を防ぐものとすること。
(4) 滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
一部改正〔平成22年規則9号〕
(安全装置)
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁でその減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で安全弁を併用したもの
一部改正〔平成22年規則9号〕
(配管の防食措置)
第10条の2 条例第31条の2第2項第9号エの規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する場合にあっては外面の腐食を防止するための塗装を行うことにより、地下に設置する場合にあっては外面の腐食を防止するための塗覆装又はコーティングにより行うものとする。
追加〔平成22年規則9号〕
(危険物の漏えいを点検できる措置)
(1) 材質は、鉄筋コンクリート製又は鉄製であること。
(2) 大きさは、直径25センチメートルの円が内接することができるものであること。
(3) 深さは、点検が十分にできるものとすること。
(4) 漏れた油が浸透しないよう防水措置がされているものであること。
(5) 雨水等が内部に浸入しないよう防水性のふたを設けること。
追加〔平成22年規則9号〕
(引火防止網)
第11条 条例第31条の4第2項第5号(
条例第3条第5項において準用する場合、第31条の5第2項においてよるものとされている場合及び第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する引火を防止するための措置は、通気管又は通気口の先端に40メッシュ程度の銅網若しくはステンレス網を張るか、又はこれと同等以上の引火防止性能を有する方法により設けること。
(液状の危険物の流出防止措置)
(1) 屋外において液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該場所の周囲には適当な傾斜をつけた溝が設けられ、かつ、ためますが設けられていること。ただし、漏れた危険物をためますに有効に導くことができる囲い等が設けられている場合は、溝を設けないことができる。
(2) 屋内において液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該室内の床に適当な傾斜がつけられ、かつ、ためますが設けられているか、又は敷居を高くする等の流出止めが設けられていること。
2 前項各号のためます等から下水等に排水する場合は、次の各号に掲げる装置を設けること。
(1) 第4類の危険物にあっては、3連式の油分離装置
(2) 第6類の危険物にあっては、中和装置
3 前項各号に掲げる装置は、随時清掃を行い、必要に応じ、油分離装置にたまった油をくみ上げ、又は中和装置の中和剤を補給する等常に機能の保持を図ること。
追加〔平成24年規則1号〕
(タンクの周囲への流出防止措置)
(1) 屋外タンクの周囲に設ける危険物の流出を防止するための有効な措置は、流出止めを次により設けること。
ア 材質は、鉄筋コンクリート造等であること。
イ 容量は、タンクの容量以上であること。ただし、2以上のタンクの周囲に設けるものにあっては、容量が最大であるタンクの全容量を収容できるものであること。
ウ 当該流出止めは、タンクの側板から0.5メートル以上離れていること。
エ 当該流出止めを貫通して配管を設けないこと。
オ 当該流出止めには、滞水を外部に排出するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁及びためます等を流出止めの外部に設けること。
(2) 屋内タンクの周囲又はタンクの室外への流出を防止するための有効な措置は、前号アからエまでの例により、流出止めを設けるほか、ためますを流出止め内に設けるものとする。
(3) 屋内タンクを設置する室外への流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。
ア タンクを設置する室の敷居を高くし、流出止めをすること。
イ タンクを設置する室の床、敷居までの高さの壁及び敷居が、コンクリート等で造られ又は覆われていること。
ウ タンクを設置する室の敷居までの高さの部分の容量は、タンクの容量以上であること。ただし、2以上のタンクを設ける場合の敷居までの高さの容量は、容量が最大であるタンクの容量以上であること。
エ タンクを設置する室の床には、ためますを設けること。
全部改正〔平成24年規則1号〕
(漏えい検査管)
(1) 材質は、金属又は硬質塩化ビニールとすること。
(2) 長さは、地盤面からタンク基盤までとすること。
(3) 構造は、小孔を有する二重管とすること。この場合、タンクの水平中心線から上部は、小孔を有する単管とすることができる。
(4) 上端部は、水が浸入しない構造とし、かつ、ふたは、点検の際容易に開放できるものとする。
(出入口の附近等)
第12条の3 条例第31条の10第1項第1号に規定する出入口の附近は、百貨店等にあっては、公共の用に供する道路又は広場に面する出入口から水平距離6メートルの範囲内とする。
2
条例第31条の10第1項第2号に規定する階段の直下及びその附近は、階段裏面の水平投影面上の空間部分及び当該階段から水平距離6メートルの範囲内とする。
(管理者が定める公示の方法)
第12条の4 省令第1条及び危険物規則第7条の5に規定する公示の方法は、消防本部及び消防署の掲示板並びにインターネットを利用する方法とする。
(管理者が定める防火対象物に係る点検事項)
第12条の5 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する基準は、次の各号に掲げるものとする。
(2)
条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。
(3)
条例第23条に規定する火の使用制限を遵守していること。
(4)
条例第26条に規定するがん具用煙火の貯蔵等に関する基準に適合していること。
(5)
条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
(6)
条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
2 前項に規定する基準に係る法第8条の2の2第1項の規定による点検は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める点検表により実施するものとする。
(1) 前項第1号から第4号までに規定する事項 点検表(
別記第3号様式)
3 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に前項の点検表を添付して行うものとする。
(個室型店舗の避難通路)
第12条の6 条例第37条の3ただし書に規定する避難上支障がないと認める外開きの戸は、次に掲げるものとする。
(1) 避難通路の片側に個室等があり、外開き戸を開放した場合に自動的に閉鎖しないものであって、開放した外開き戸と避難通路の内壁との有効幅員をおおむね60センチメートル以上確保することができるもの
(2) 避難通路の両側に個室等があり、外開き戸を開放した場合に自動的に閉鎖しないものであって、開放した両側の外開き戸の有効幅員をおおむね60センチメートル以上確保することができるもの
(3) 前号において開放した外開き戸により避難通路の有効幅員を確保できないものであっても、いずれか片側の個室等の外開き戸を自動的に閉鎖する措置を講じることにより有効幅員をおおむね60センチメートル以上確保することができるもの
追加〔平成24年規則1号〕、一部改正〔平成30年規則8号〕
(施錠に関する基準)
第12条の7 条例第40条第4号ただし書に規定する屋内から鍵等を用いることなく容易に解錠できる構造は、次の表のア欄に掲げる戸の区分に応じイ欄に掲げる構造とする。ただし、人が常時監視し、非常の際容易に解錠できる構造のものにあっては、この限りでない。
ア | イ |
(1) 屋内避難階段に通ずる戸 | 鍵等を用いず屋内から一つの動作で容易に解錠できるもの。ただし、地階又は無窓階にあっては、鍵等を用いず屋内から開放動作で解錠し、開放できるもの |
(2) 特別避難階段に通ずる戸 |
(3) 屋外階段に通ずる戸 | 鍵等を用いず屋内から開放動作で解錠し、かつ、開放できるもの |
(4) 非常の際に避難専用とするために設けた戸((1)から(3)までに掲げるものを除く。) |
追加〔平成24年規則1号〕、一部改正〔平成26年規則5号〕
(避難経路図)
(1) 避難施設及び避難器具の設置位置
(2) 避難経路
(3) 宿泊者に対する火災の伝達方法
(4) 避難上の留意事項
一部改正〔平成22年規則9号〕
(指定催しの指定等)
2
条例第42条の4第3項の規定による公示の方法は、消防本部及び消防署の掲示板並びにインターネットを利用する方法とする。
3 前項に規定する方法により公示する内容は、次の各号に掲げる内容とする。
(1) 指定催しの名称及び開催場所
(2) 指定催しの開催期間及び開催時間
(3) その他消防長が必要と認める事項
追加〔平成26年規則7号〕
(防火対象物の使用開始等の届出)
第14条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出又は変更の届出は、防火対象物使用開始(変更)届出書(
別記第6号様式)により届け出るものとする。
一部改正〔平成19年規則18号・22年9号〕
(工事中の消防計画の届出)
一部改正〔平成19年規則18号〕
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事計画の届出)
第14条の3 条例第46条の2に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事計画の届出は、消防用設備等(特殊消防用設備等)工事計画届出書(
別記第8号様式)により届け出るものとする。
2 前項の消防用設備等(特殊消防用設備等)工事計画届出書に添えなければならない図書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 消防用設備等 次に掲げるもの
ア 案内図、付近見取図、平面図及び立面図又は断面図
イ 消防用設備等の工事の設計に関する図書
(2) 特殊消防用設備等 次に掲げるもの
ア 案内図、付近見取図、平面図及び立面図又は断面図
イ 特殊消防用設備等の工事の設計に関する図書、設備等設置維持計画(法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画をいう。)、法第17条の2第3項の評価結果を記載した書面及び法第17条の2の2第2項の認定を受けた者であることを証する書類の写し
全部改正〔平成19年規則18号〕、一部改正〔平成22年規則9号〕
(消防訓練の届出)
一部改正〔平成19年規則18号〕
(火を使用する設備等の設置又は変更の届出)
一部改正〔平成19年規則18号・22年9号・令和3年4号〕
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第17条 条例第45条各号に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の様式により届け出るものとする。ただし、
同条第1号及び
第4号に関わる行為にあっては、当該届出書の提出にかえて口頭により行うことができる。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為にあっては、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(
別記第13号様式)
(2) 煙火の打上げ、又は仕掛けにあっては、煙火打上げ・仕掛け届出書(
別記第14号様式)
(3) 劇場等以外の建物、その他の工作物における催物の開催にあっては、催物開催届出書(
別記第15号様式)
(4) 水道の断水、又は減水にあっては、水道断水・減水届出書(
別記第16号様式)
(5) 消防隊の通行、その他消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事にあっては、道路工事届出書(
別記第17号様式)
(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設にあっては、露店等の開設届出書(
別記第17号様式の2)
2 前項の届出は、それぞれ当該行為を行う日の3日前までに届け出なければならない。ただし、その行為を行うことが急を要するときは、その行為を行う当日までに届け出ることができる。
一部改正〔平成19年規則18号・24年1号・26年7号〕
(指定洞道等)
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、
条例第45条の2第2項において準用する
同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概要図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な設備の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び従業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
一部改正〔平成19年規則18号〕
(指定数量未満の危険物等の貯蔵、取扱いの届出)
第18条 条例第46条第1項に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵、取扱い又はその変更の届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵、取扱い(変更)届出書(
別記第19号様式)により届け出るものとする。
一部改正〔平成19年規則18号〕
(核燃料物質等の貯蔵、取扱いの届出)
第18条の2 条例第46条の4の規定による核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液化ガス、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で消防長の指定するものの貯蔵、取扱い又はその変更の届出は、核燃料物質等貯蔵、取扱い(変更)届出書(
別記第20号様式)により届け出るものとする。
一部改正〔平成19年規則18号〕
(廃止の届出)
2
条例第46条第2項に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵、取扱いの廃止の届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵、取扱い廃止届出書(
別記第23号様式)により届け出るものとする。
3
条例第46条の4の規定による核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液化ガス、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で、消防長の指定するものの貯蔵、取扱いを廃止しようとするときは、核燃料物質等貯蔵、取扱い廃止届出書(
別記第24号様式)により届け出るものとする。
一部改正〔平成19年規則18号〕
(タンクの水張検査等の申請)
2 消防長は、前項の申請を受けたときは検査を行い、
条例に規定する基準に適合していると認めたときは、タンク検査済証(
別記第26号様式)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成19年規則18号・22年9号〕
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第21条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2
条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
追加〔平成30年規則8号〕
(公表の手続)
(1) インターネットを利用する方法
(2) 消防本部及び消防署で閲覧に供する方法
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(該当違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
追加〔平成30年規則8号〕
(委任)
第23条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
一部改正〔平成30年規則8号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。
2 山武郡市広域行政組合火災予防条例施行規則(昭和60年山武郡市広域行政組合規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成4年規則第8号)
この規則は、平成4年5月25日から施行する。
附 則(平成6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第7条の改正規定、第8条の改正規定、第9条の改正規定、第10条の改正規定、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第12条の2を追加する改正規定及び別記様式を加える改正規定(別記第18号様式、別記第22号様式、別記第23号様式及び別記第24号様式を除く。)は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第7条の6の次に1条を加える改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山武郡市広域行政組合火災予防条例施行規則別記第2号様式、第6号様式から第26号様式までに規定する様式は、第1項の規定にかかわらず、平成18年6月30日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山武郡市広域行政組合火災予防条例施行規則別表第1の規定にかかわらず、施行日前に設けられた標識の様式は、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月26日規則第7号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条を第23条とし、第20条の次に2条を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の山武郡市広域行政組合火災予防条例施行規則別表第1の規定にかかわらず、施行の日の前に設けられた標識については、当分の間、なお従前の例によることができる。
3 第1条の規定による改正後の山武郡市広域行政組合火災予防条例施行規則別記第2号様式から第7号様式(その1)まで、別記第8号様式(その1)及び別記第9号様式から第25号様式までに規定する様式並びに第2条の規定による改正後の山武郡市広域行政組合危険物規制規則別記第1号様式、別記第12号様式及び別記第18号様式(その1)から第23号様式までに規定する様式は、第1項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(令和3年3月19日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別記様式中「

」を削る規定及び別記第5号様式の2を改正する規定については、公布の日から施行する。
別表第1(第4条第1項)
区分 | 標識 |
サウナ室への新聞雑誌等持込厳禁及び禁煙の標識 | 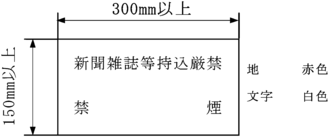
|
燃料電池発電設備の標識 | 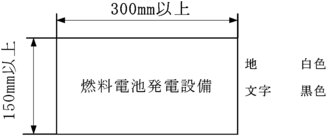
|
変電設備の標識 | 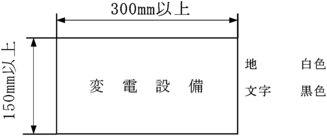
|
急速充電設備の標識 | 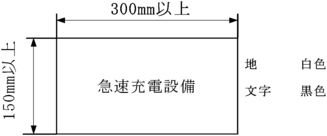
|
発電設備の標識 | 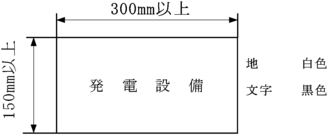
|
蓄電池設備の標識 | 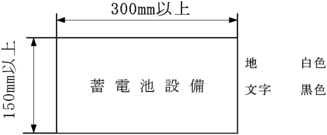
|
水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止の標識 | 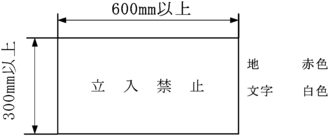
|
禁煙の標識 | 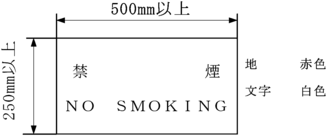
|
裸火使用厳禁の標識 | 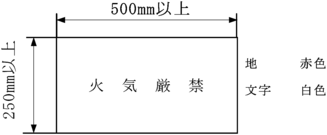
|
危険物品持込み厳禁の標識 | 
|
禁煙、裸火使用厳禁及び危険物品持込み厳禁の標識 | 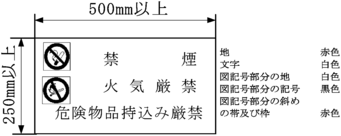
|
喫煙所の標識 | 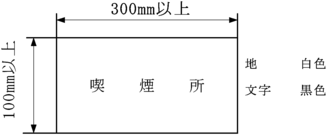
|
危険物を貯蔵し又は取り扱っている場所の標識 | 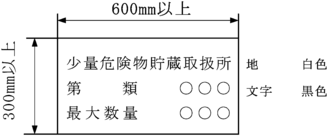
|
指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場所の標識 | 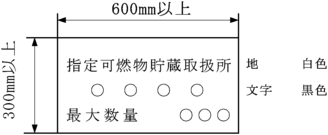
|
全部改正〔令和元年規則3号〕
別表第2(第4条第2項)
禁水の掲示板 | 火気注意の掲示板 |
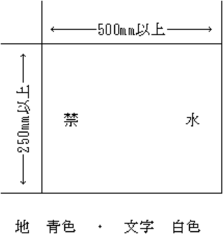
| 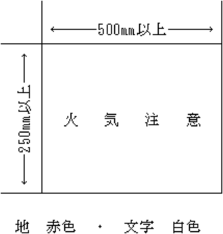
|
火気厳禁の掲示板 | 火気注意及び整理整とんの掲示板 |
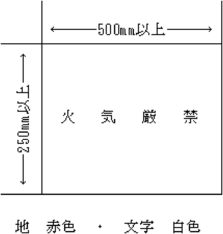
| 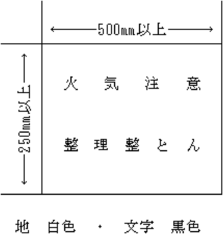
|
別表第3(第4条第3項)
定員の表示板 |
表 | 裏 |
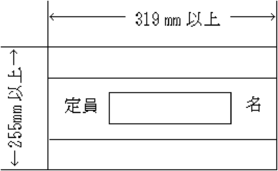
| 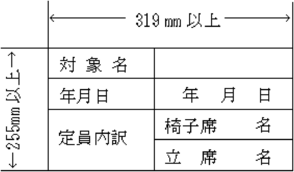
|
横線及び定員枠 金色 上部及び下部の地 白色 中央部の地 赤色 |
満員札 |
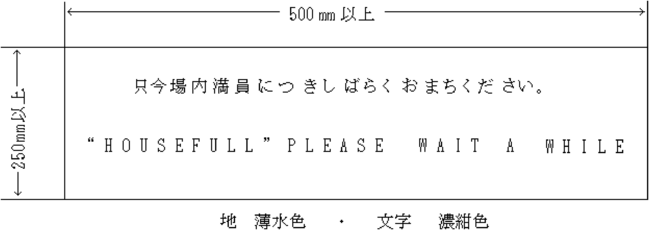
|
別記
第1号様式 削除
削除〔平成22年規則9号〕
 第2号様式
第2号様式(第7条の5)
全部改正〔平成22年規則9号〕、一部改正〔平成30年規則8号・令和元年3号・3年4号〕
 第3号様式
第3号様式(第12条の5)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号〕
 第4号様式
第4号様式(第12条の5)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号〕
 第5号様式
第5号様式(第12条の5)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号〕
 第5号様式の2
第5号様式の2(第13条の2第1項)
全部改正〔令和3年規則4号〕
 第5号様式の3
第5号様式の3(第13条の2第4項)
追加〔平成26年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則3号・3年4号〕
 第6号様式(その1)
第6号様式(その1)(第14条)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第6号様式(その2)
第6号様式(その2)(第14条)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号〕
 第7号様式(その1)
第7号様式(その1)(第14条の2)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第7号様式(その2)
第7号様式(その2)(第14条の2)
 第7号様式(その3)
第7号様式(その3)(第14条の2)
 第7号様式(その4)
第7号様式(その4)(第14条の2)
 第8号様式(その1)
第8号様式(その1)(第14条の3)
全部改正〔平成19年規則18号〕、一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第8号様式(その2)
第8号様式(その2)(第14条の3)
一部改正〔平成19年規則18号・22年9号〕
 第9号様式
第9号様式(第15条)
全部改正〔令和元年規則3号〕、一部改正〔令和3年規則4号〕
 第10号様式
第10号様式(第16条)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第10号様式の2
第10号様式の2(第16条)
追加〔平成22年規則9号〕、一部改正〔令和元年規則3号・3年4号〕
 第11号様式
第11号様式(第16条)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第12号様式
第12号様式(第16条)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第13号様式
第13号様式(第17条第1項第1号)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第14号様式
第14号様式(第17条第1項第2号)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第15号様式
第15号様式(第17条第1項第3号)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第16号様式
第16号様式(第17条第1項第4号)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第17号様式
第17号様式(第17条第1項第5号)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第17号様式の2
第17号様式の2(第17条第1項第6号)
追加〔平成26年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則3号・3年4号〕
 第18号様式
第18号様式(第17条の2第1項)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第19号様式
第19号様式(第18条)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第20号様式
第20号様式(第18条の2)
一部改正〔平成19年規則18号・22年9号・令和元年3号・3年4号〕
 第21号様式
第21号様式(第19条第1項)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第22号様式
第22号様式(第19条第1項)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第23号様式
第23号様式(第19条第2項)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第24号様式
第24号様式(第19条第3項)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第25号様式
第25号様式(第20条第1項)
一部改正〔平成22年規則9号・令和元年3号・3年4号〕
 第26号様式(正)
第26号様式(正)(第20条第2項)
一部改正〔平成22年規則9号〕
 第26号様式(副)
第26号様式(副)(第20条第2項)
一部改正〔令和元年規則3号〕
 」を削る規定及び別記第5号様式の2を改正する規定については、公布の日から施行する。
」を削る規定及び別記第5号様式の2を改正する規定については、公布の日から施行する。