○自動火災報知設備等の作動と連動して行う通報等の承認に関する規程
平成18年6月14日訓令第4号
自動火災報知設備等の作動と連動して行う通報等の承認に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、山武郡市広域行政組合火災予防条例(昭和48年山武郡市広域行政組合条例第10号。以下「条例」という。)第46条の3に規定する自動火災報知設備の作動と連動して行う通報等の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通報区分)
第2条 自動火災報知設備等の作動と連動して行う通報の区分については、次の各号に掲げるものとする。
(1) 即時通報 防火対象物が無人状態にあるとき、当該防火対象物に設置された自動火災報知設備の火災信号を警備業者、第3セクター等の第三者機関(以下「警備業者等」という。)が受信し、火災の確認を行うことなく消防機関に通報するものをいう。
(2) 有人直接通報 病院及び社会福祉施設等で自力避難が困難な者が多数入院、入所等し、又は多数の者が出入りし、若しくは居住する有人の防火対象物に設置された自動火災報知設備の火災信号により火災通報装置(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第25条第3項に定める火災通報装置をいう。以下同じ。)が作動し直接消防機関に通報するものをいう。
(3) 無人直接通報 防火対象物が無人状態にあるとき、当該防火対象物に設置された自動火災報知設備の火災信号により火災通報装置が作動し直接消防機関に通報するものをいう。
(承認の要件)
第3条 即時通報、有人直接通報及び無人直接通報(以下「即時通報等」という。)を認める防火対象物は、次の各号に掲げる要件に該当しなければならない。
(1) 即時通報を認める防火対象物は、次に掲げる要件すべてに該当するものとする。
ア 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の規定により、又は当該規定に準じて自動火災報知設備が防火対象物全体に設置され、及び維持されていること。
イ 自動火災報知設備には、非火災報防止対策が講じられていること。
ウ 自動火災報知設備の作動信号を遠隔通報装置に送信する機器等は、設置及び維持管理が適正になされていること。
エ 消防機関へ通報後、適切な対応ができる関係者又は警備業者等が速やかに現場到着できる体制であること。
オ 消防隊が到着後速やかに自動火災報知設備の受信機に到達できる手段(自動火災報知設備連動開錠装置等)が確保されているか、又は防火対象物内の異状の有無を確認するための必要な破壊を承諾することができること。
カ 第6条に規定する即時通報を行う警備業者等の登録をされている警備業者等が行うものであること。ただし、通報を行う警備業者等を当該登録を受けた警備業者等とすることができない場合は、同条第3項に掲げる事項に適合する者とすることができる。
キ 防火管理が適正に実施されていること。
(2) 有人直接通報を認める防火対象物は、次に掲げる要件すべてに該当するものとする。
ア 法第17条の規定により、又は当該規定に準じて自動火災報知設備が防火対象物全体に設置され、及び維持されていること。
イ 自動火災報知設備には、非火災報防止対策が講じられていること。
ウ 自動火災報知設備の作動信号を火災通報装置に送信する機器等は、設置及び維持管理が適正になされていること。
エ 防火管理が適正に実施されていること。
(3) 無人直接通報を認める防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物のうち、次に掲げる要件すべてに該当するものとする。
ア 法第17条の規定により、又は当該規定に準じて自動火災報知設備が防火対象物全体に設置され、及び維持されていること。
イ 自動火災報知設備には、非火災報防止対策が講じられていること。
ウ 自動火災報知設備の作動信号を火災通報装置に送信する機器等は、設置及び維持管理が適正になされていること。
エ 消防機関へ通報後、当該防火対象物の関係者等にも通報され、適切な対応ができる関係者が速やかに現場到着できる体制であること。
オ 消防隊が到着後速やかに自動火災報知設備の受信機に到達できる手段(自動火災報知設備連動開錠装置等)が確保されているか、又は防火対象物内の異状の有無を確認するための必要な破壊を承諾することができること。
カ 防火管理が適正に実施されていること。
(通報先の指定)
第4条 条例第46条の3に規定する消防長等が指定する場所は、山武郡市広域行政組合消防本部、消防署、分署及び出張所とする。
(承認の申請)
第5条 即時通報等の承認を受けようとする防火対象物の権原者は、次の通報の区分に応じた申請書を2通作成し、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)に提出しなければならない。
(2) 有人直接通報 有人直接通報承認申請書(別記第3号様式)
(3) 無人直接通報 通報承認申請書及び無人直接通報に係る体制(別記第4号様式)
(即時通報を行う者の登録)
第6条 即時通報を行う警備業者等は、消防長の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする警備業者等は、即時通報登録申請書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付したものを2通作成し、消防長に提出しなければならない。
(1) 会社の概要及び業務内容を記載した書類
(2) 待機所の所在及び名称を記載した書類
(3) 受信場所及び待機所ごとの従業員数を記載した書類
(4) 待機所ごとの配置車両及び通報対象となる防火対象物名を記載した書類
(5) 受信場所及び待機所の対応状況を記載した書類
(6) 遠隔通報装置、受信装置及び連絡に用いる機器の概要及び機器ごとの仕様図書
(7) その他消防長が必要と認めるもの
3 消防長は、前項の登録の申請があった場合において、申請者が次の各号に掲げる要件を満たしているときは、登録番号、登録年月日及び即時通報登録申請書の記載事項を登録簿に登録するものとする。
(1) 防火管理及び火災対応に関する十分な知識及び能力を有していること。
(2) 即時通報に係る適切な体制を有していること。
(3) 即時通報に用いる機器等の設置及び維持管理が適正であること。
4 消防長は、前項の規定による登録をしたときは即時通報登録通知書(別記第6号様式)に即時通報登録申請書の1通を添付し申請者に交付する。登録をしないときは、即時通報登録申請書の1通に登録しない理由を付して申請者に交付する。
5 登録された警備業者等は、登録の内容に変更があったときは、即時通報登録内容変更届出書(別記第7号様式)により、速やかにその旨を消防長に届け出るものとする。
6 消防長は、登録された警備業者等が第3項の登録要件を満たさなくなったとき、又は登録の継続が不適当であると認められる事由が生じたときは当該登録を取り消すことができる。なお、取消しをするときは当該警備業者等に取消しする旨を通知するものとする。
7 登録の有効期間(次項の規定により登録の有効期間が更新された場合にあっては、当該更新された登録の有効期間。以下同じ。)は、登録を受けた日(登録の有効期間が更新された場合にあっては、更新する前の登録の有効期間が満了した日の翌日)から起算して3年とする。
8 登録の有効期間の更新を受けようとする警備業者等は、当該登録の有効期間が満了する日の30日前までに消防長に申請しなければならない。
(即時通報等承認の通知)
第7条 消防長等は、第5条の申請を承認したときは、速やかに即時通報等承認通知書(別記第8号様式)に申請書の1通を添付し申請者に交付する。
(承認後の変更届出)
第8条 即時通報等の承認を受けた警備業者等は、承認後、申請書又は添付書類の記載事項に変更が生じたときは、通報承認内容変更届出書(別記第9号様式)により、速やかに消防長等に届け出なければならない。
(承認の取消し)
第9条 消防長等は、承認対象物が第3条の承認要件を満たさなくなったとき又は不適当と認められる事由が生じたときは、承認を取り消すことができる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年3月19日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、公示の日から施行する。(後略)
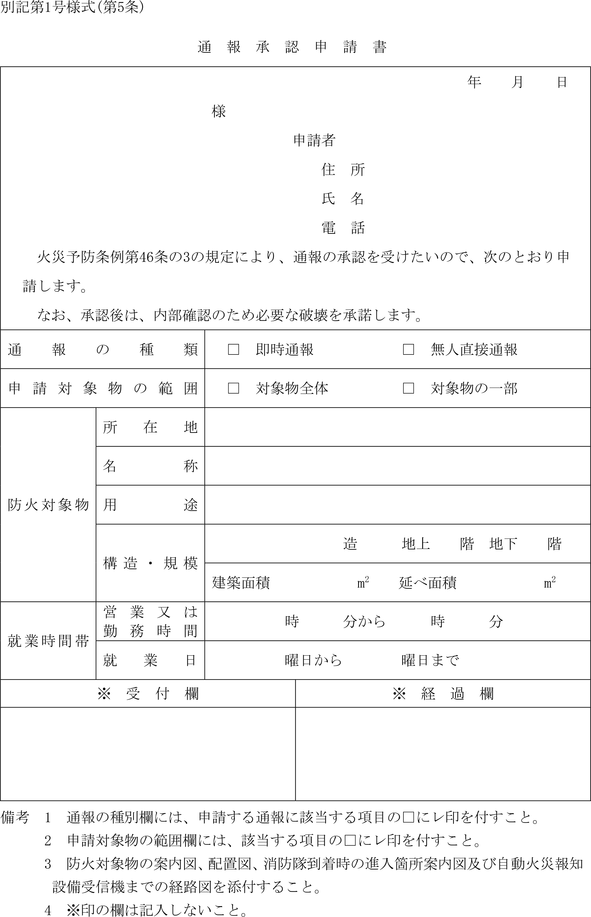
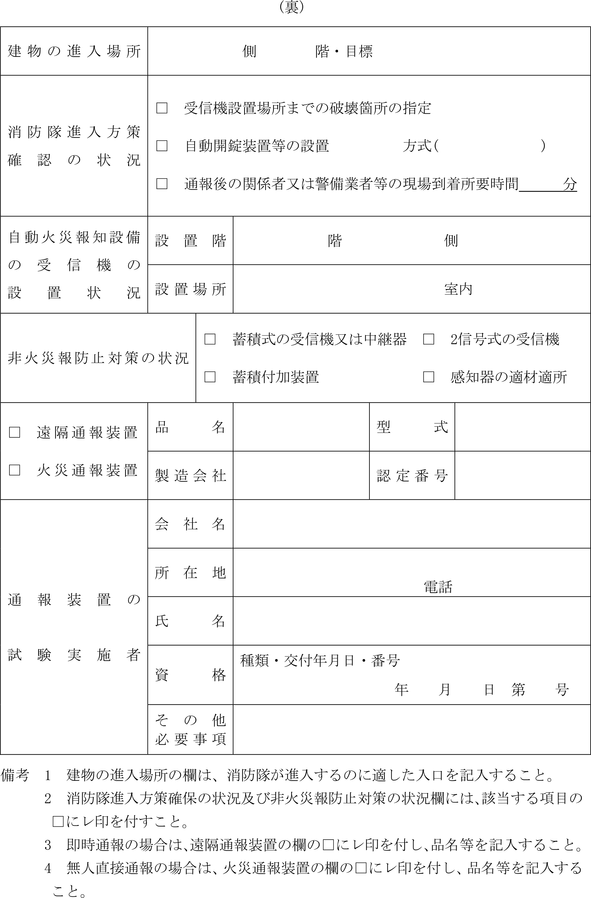
一部改正〔令和3年訓令3号〕
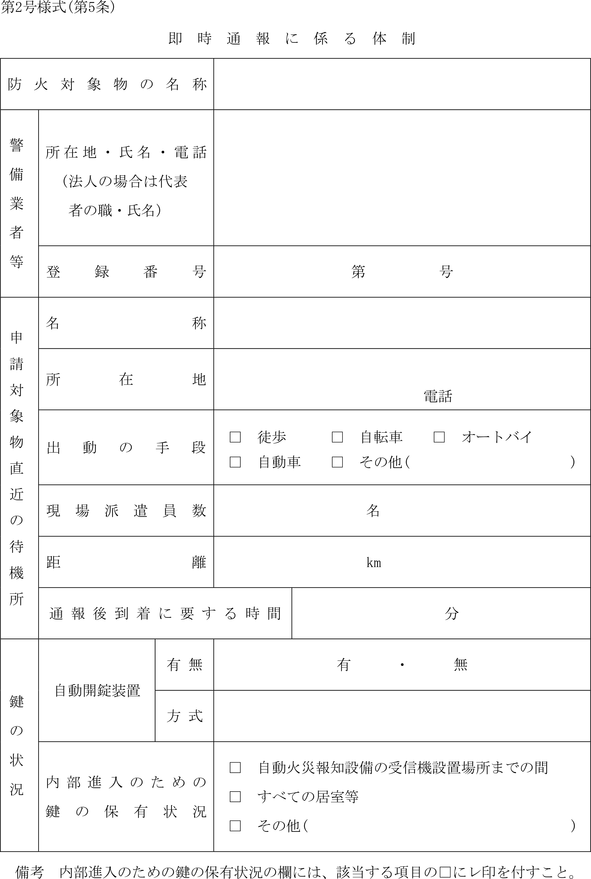
一部改正〔令和3年訓令3号〕
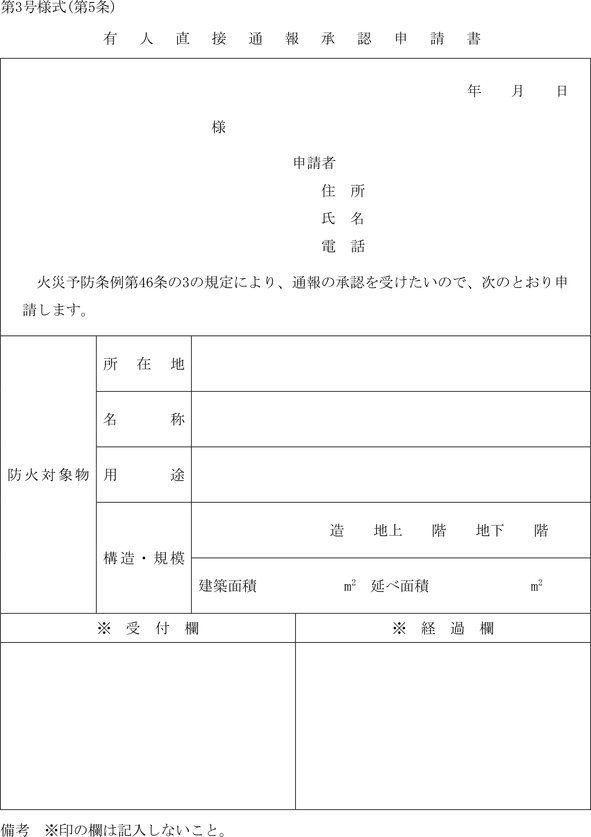
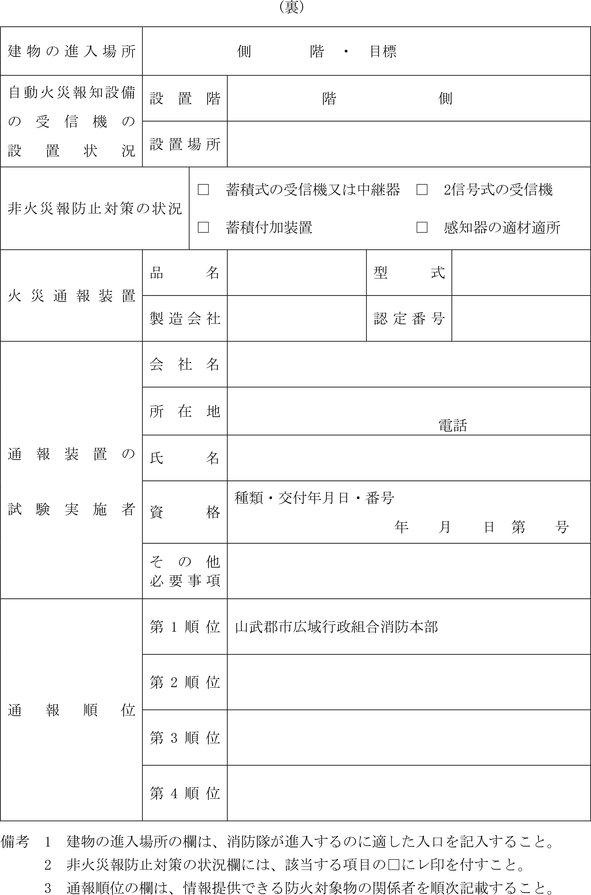
一部改正〔令和3年訓令3号〕
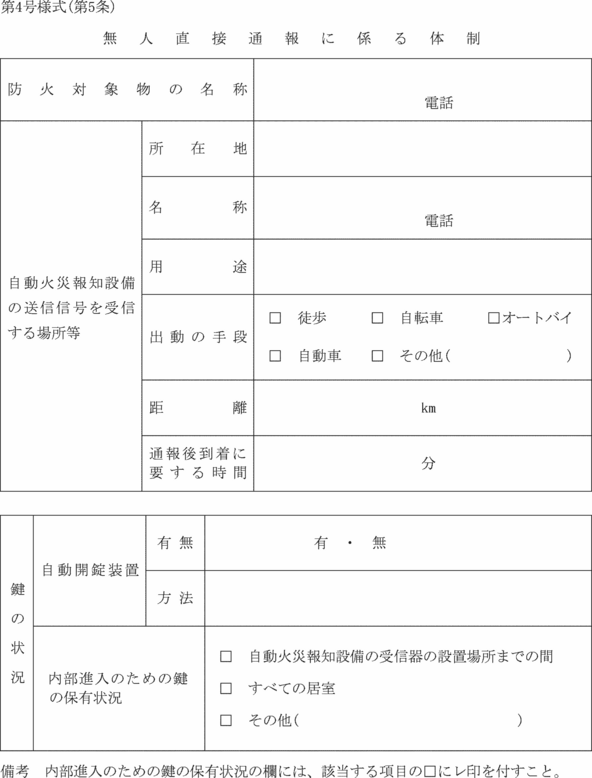
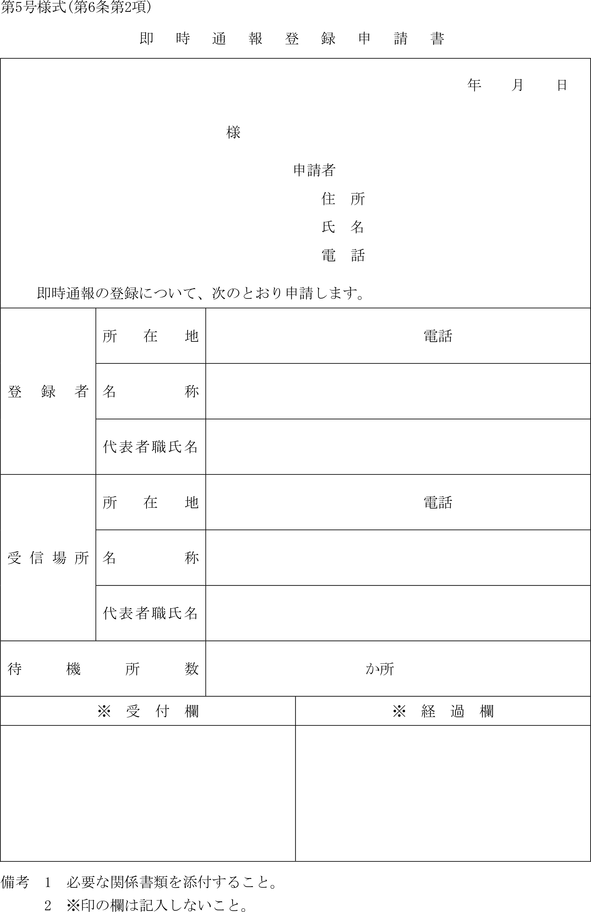
一部改正〔令和3年訓令3号〕
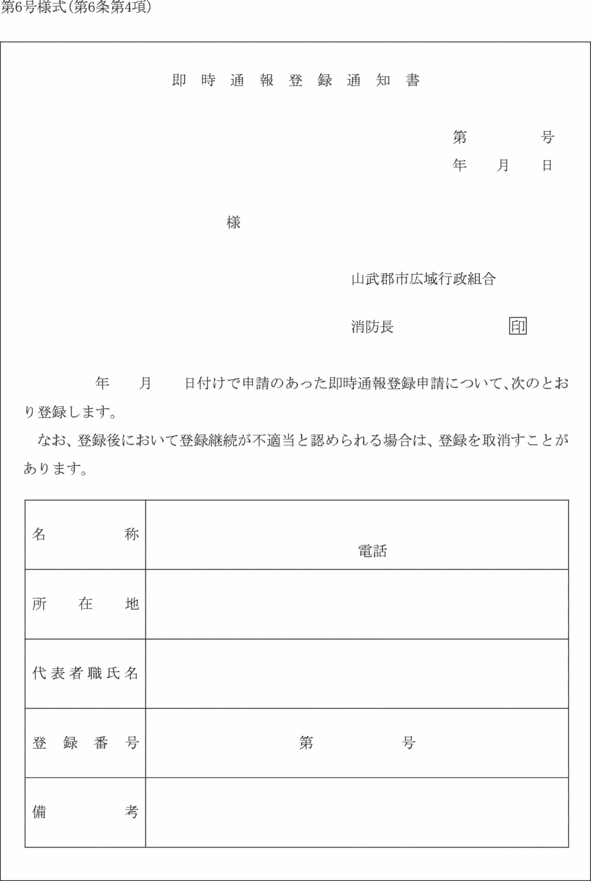
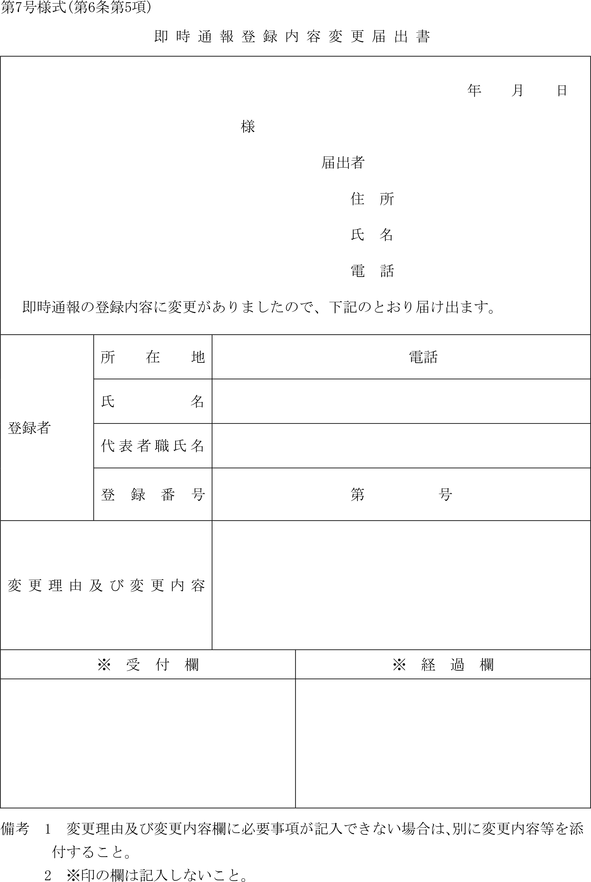
一部改正〔令和3年訓令3号〕
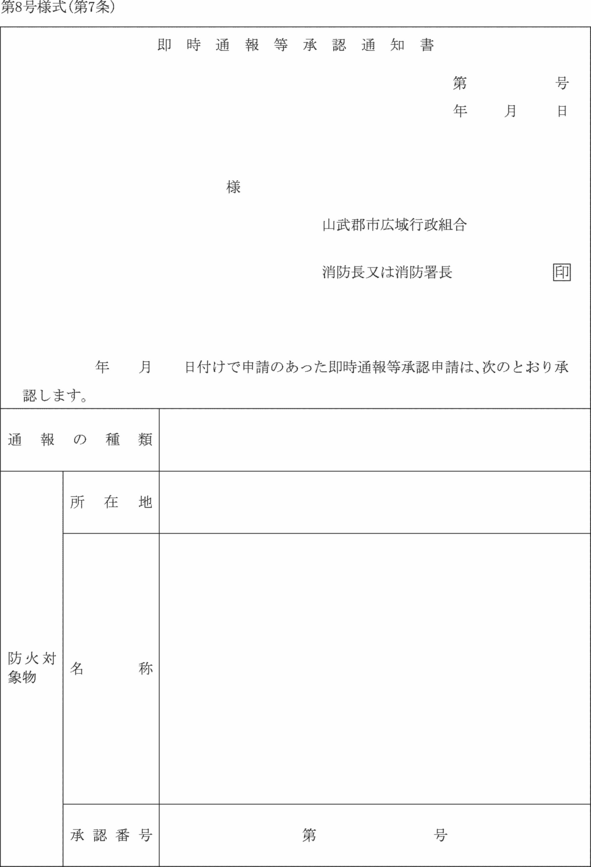
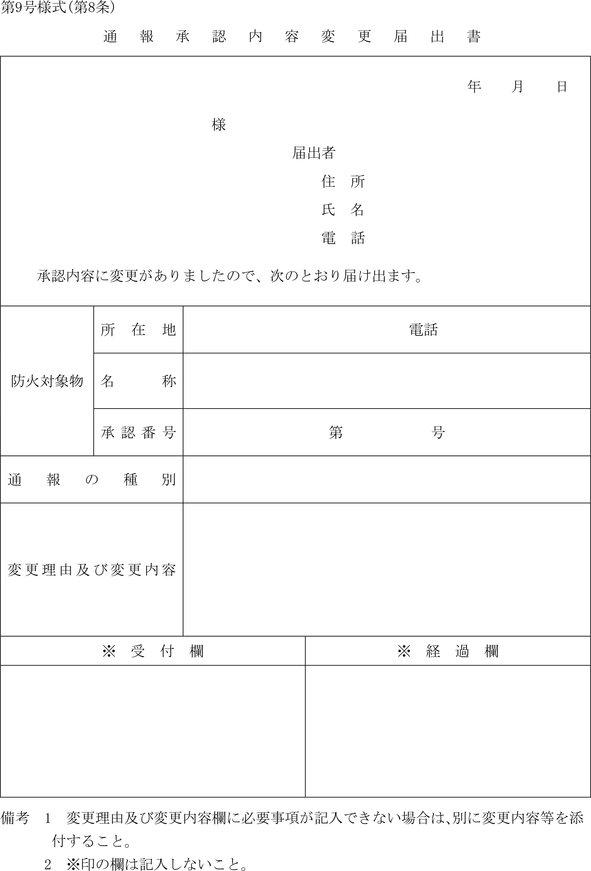
一部改正〔令和3年訓令3号〕
